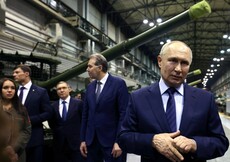――トランプ大統領就任後、映画人の発言で変わったと感じることはありますか?
藤:こちらから聞かなくても、俳優や監督、プロデューサーさんたちのほうからトランプ大統領について話すことが多くなりましたね。これまでも彼らが自ら政治的な問題について話す傾向はありましたが、さらに強まった感があります。
ただ最近は、そうした発言をすればするほど、反感を買ってしまう状況が一方で生まれています。
この4月、ナチス政権下の普通の人々の静かなる抵抗を描いた、7月公開の『ヒトラーへの285枚の葉書』の監督、フランス在住のヴァンサン・ペレーズにインタビューしました。フランス大統領選の決選投票の直前だったので、選挙をめぐる状況に話が及びました。彼が言うには、国民戦線のマリーヌ・ルペンを支持するフランスの映画人は見たことがないが、みんなあえて語らないようにしている、と。アメリカで著名人が反トランプを言い過ぎたことによる「教訓」からだそうです。
社会階層が固定化して格差が広がるなか、多くの失業者もいる一方で、著名な映画人は彼らの月収を瞬時に稼いでしまう。そうした著名人が、いくら反トランプを訴えたところで、反感を買ってしまうだけだという状況が起きています。
だから、フランスの映画人たちは、静かにしていると。あまりに熱くなりすぎて、ハリウッドの二の舞いにはなりたくない。でも、あまりに冷めていても……と。その間合いが難しいと語っていました。そういった意味でも転換期にあるのかもしれません。
――中国経済が急成長し、ハリウッド映画への中国マネーの影響が指摘されてきましたが、現状はどうなのでしょうか?
藤:中国マネーが映画市場を席巻し始めた頃は、プロットを中国に配慮して変更したり、中国製品が登場する場面を挿入したり、はては中国人俳優の出演場面を中国向けに追加したり、なんてことがよくありました。そのほうが中国で上映されやすいという考え方は確かに未だにあります。ただ、そうしたあからさまな中国への配慮を、中国の良識派も嫌がるにようにはなってきています。
南北戦争のさなか、貧しい白人と黒人がともに南軍に反旗を翻した戦いを描いた『ニュートン・ナイト 自由の旗をかかげた男』の製作総指揮者をインタビューした時に、中国マネーの増加が実は、アメリカで減りつつある「大人の映画」を支えてもいるのだと知りました。この映画の米国での配給は、STXエンターテイメントという新興のアメリカの映画会社が担いました。この会社にはアメリカや中国の投資ファンドが出資しています。16年には中国のIT大手テンセントや香港の通信大手PCCWからも出資を受けています。
また、製作には「中国のワーナー・ブラザーズ」と言われる華誼兄弟伝媒という中国の大手映画会社が加わりました。
STXが設立されたのは、一定のヒットが確実視される続編・リメイクに資金が注がれ、「大人の映画」がなかなか製作されない今のハリウッドをなんとかしたいためだといいます。
昨今、中国のハリウッドへの投資には、ハリウッドの映画作りのノウハウを学ぼうという意図もあります。
確かに、アメリカの映画館大手チェーンや映画製作会社を買収した万達グループは、一般的には中国政府寄りと見られてはいます。しかし、中国マネーと一口に言っても、いわば「安全圏」に入り込みがちなハリウッドの幅を広げている場合も出てきていますから、一概に問題があるとは言えません。実はかえってよくなっている面もあるというのは、大きな発見でしたね。
――出版後の反響はどうですか?
藤:日本の映画人にも、ハリウッドをはじめとする世界の映画人のようにどんどん発言して欲しい、という声はよく聞こえてきます。一連のインタビューで感じるのは、私が社会にからめて質問すると、喜んで答えてくれる場合が多いなということです。つまり、発言は無理やり聞き出しているのではなく、彼らの自発によるところが大きい。日本と大きく違う、そうした面もわかってもらえればと思いますね。社会的・政治的に発言するというのは、彼らにとっては標準装備なんです。
この本は、映画を見ていなくても、あるいは関心がなくても世界情勢がわかるように、そして世界情勢がわからなくても、映画を通して見ればもっと身近に感じるように書きました。世界を知るひとつの手段として、ぜひ手にとってもらえればと思います。
■修正履歴
2ページ目「マッカーサーの赤狩り」は正しくは「マッカーシーの赤狩り」でした。お詫びして訂正致します。該当箇所は修正済みです。(2017/07/07)
![]()
![]()
![]()
▲「WEDGE Infinity」の新着記事などをお届けしています。