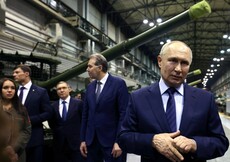中国で出版された『不愉快な中国』
例えば一昨年、中国の極端なナショナリズムを代表する論客である王小東・宋暁軍らは『中国不高興(不愉快な中国)』を刊行し、「チベット問題は西側の中国包囲戦略がますます具体化し猖獗(しょうけつ)している現れである」「サルコジの中国に対する度重なる侮辱は野卑で下流な機会主義である」と切って捨てるとともに、中国は西側を制するためにも「遠大な抱負を抱いた英雄的国家たれ」「剣を片手に通商に従事することこそ、《崛起(くっき)》する大国の勝利の道である」「解放軍は中国の核心利益とともに歩め」と強硬に主張している。彼らの主張を共産党が正面から認めているわけではないが、諸外国における中国脅威論を明らかに加速させる強硬論を今以て放置していること自体は暗黙の承認に等しく、中国共産党・政府内部の対外強硬論と民間ナショナリズムの強硬論が約20年来の様々な動きを経て接近していることを示している。
とりあえず『中国不高興』に対しては、「ネット上の憤青(憤怒青年)をいたずらに鼓舞するのみで、中国の真の大国化と国際化に寄与しない」という反論(とくに大都市の「知識界」による)も相次いで出版され、それなりに反響を呼んでいるのも確かである。しかし、それは極めて限られた広がりの議論にとどまり、党と政府によってコントロールされた中国の言論空間で主流となるには至っていない。
しかし、90年以来そのような長期的目標に則して動いたところで、共産党体制の本質を変えないまま最初から「他国に侮られず、むしろ自らが国際関係を制する」大国としての顔を見せるのであれば、そのような中国を信頼できる協力相手と見なして投資・技術協力・経済援助しようとは誰も思わないだろう。そこで、少なくとも表向き「中国はグローバリズムの論理に忠実な存在である」「中国は発展途上国である以上、他国に対し傲慢に振る舞う余裕はなく、むしろ中国の発展が他国の発展や国際関係の安定にも結びつく」という説明が「真実」であると受け取られることが欠かせなかった。
したがって、中国が最近まで掲げてきた対外関係の原則「韜光養晦(とうこうようかい・才能を隠して表に出さない)」は、今改めて振り返ってみると、まさにこのような「他国を制する大国として《崛起》する」という目標を果たすために、当面は低姿勢な《良きパートナー》のふりに徹し、いつしか長期的な対抗相手である西側を惑わせる、という発想の現れに過ぎなかったように思われる。
中国外交の言行不一致
ここ数年来の日中関係を丁寧に読み解けば、このような中国外交の性格が滲み出ているはずであったが、尖閣問題が起こるまで日本国内で必ずしも深刻に捉えられなかったのは、逆に日本の側の長期的戦略や複眼的思考の欠如によるものであろうか?
今から6年前、日本の国連常任理事国入り問題や所謂「歴史認識」問題で日中関係が揺れ、とくにサッカー・アジア杯での衝突から「愛国無罪」の反日デモへと事態がエスカレートした。この過程における中国の対日外交は、「平和的で理性的である(彼らはそう主張する)」どころか、根拠なき「日本軍国主義の蔓延」を前面に押し出して執拗に日本を非難・攻撃し、日本の国際的イメージを失墜させようとするものであった。
それ自体は明らかに、建設的な批判を通じて日本との関係を調整するという性格のものではなく、隙あらば他国を凌駕して自国が圧倒的に制する側に回ろうとする発想の現れであったが、そのさなかに胡錦濤政権が強く主張しはじめ、今日まで掲げてきた「和平発展」なるスローガンが一層外部の判断を惑わせてきた。「中国の経済発展と軍事力は世界にとって有利であり、中国は世界の如何なる国家とも衝突することを望まない。Win-Winの関係を構築する」という方針とは裏腹に、隣国との関係をなりふり構わず傷つけようとする現実の中国外交の手法は言行不一致そのものではなかったか。