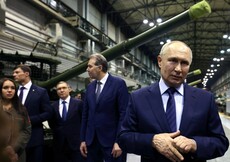食べてゆく為のあらゆる責任を双肩に担った
46(昭和21)年10月、復員官を依頼免官し、郷里の鳥取県境港に戻った。自分自身にとっての復員であり、父は22歳4カ月だった。
郷里には祖母(72歳)、妹2人(17歳、15歳)、身重の妻(21歳)が待っていた。
「その日から食べてゆく為のあらゆる責任を双肩に担った」
以後の8年間は苦闘の連続だった。芋飴の製造・販売、土建業現場監督、地元の海運業、小さな石油会社勤務など職を転々とした(47年、1歳10カ月の長女が栄養不良で死亡)。
私は長女(姉)の死の翌年に生まれたが、父が公私ともに安定するのは54年に海上警備隊(後の自衛隊)に入隊して以降である。
今振り返ると、父の復員官時代はシャバ(一般社会)への軟着陸の時期だったのかもしれない。「盡忠玉砕」しか頭になかった職業軍人が、敗戦を納得し、家族(4人の女性) のために再出発を決意するまでの必要な時間……。
田端義夫の『かえり船』は故国を前にした復員兵の思いを歌った往年のヒット曲だが、復員船の乗組員の側にも屈折し錯綜した思いがあったことを、今回私は知った。
それもこれも父が『自分史』を遺してくれたからだ。
86歳で亡くなった父の生前、私もあまり父親と話したことはなかった。母親よりずっと話しにくい相手だった。だが、取材で知った『記入式自分史ノート』を手渡すと、当時71歳だった父は少しづつ書き進めたのだ。
目に見えない「人生」も、文字に残してあれば確認できる。
![]()
![]()

▲「WEDGE Infinity」の新着記事などをお届けしています。