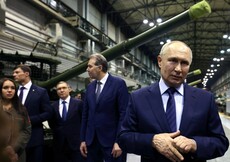かん口令がしかれ、タブーになったまま
なぜ、この雑誌の編集者たちはたった40社ほどのベンチャー企業を熱狂的に報じ続けたのだろうか。そこには様々な要因が折り重なっていたのだろうが、大きな理由の1つに、この出版社の社内の事情があったのではないかと私は見ている。
一言でいえば、ずさんな人事評価や配置転換、昇進・昇格などに愛想がつき、「隣の芝生は青い」のような思いで、ベンチャー企業をうらやましく見ていたのだと思う。その意識が、記事や雑誌の随所に出ていたのではないだろうか。つまり、ある意味で「悲鳴」であり、「溜息」であり、「あきらめ」の念が雑誌には凝縮していたように私には見えるのだ。
この雑誌を発売する出版社は、比較相対的に高学歴な社員が多いこともあり、20代の頃の意識はある程度は高い。しかし、30代になるとやる気を失い、失速する人が増えてくると退職した元社員5人ほどは語る。社内の人事の仕組み(人事評価や育成、配置転換など)は相当にお粗末で、ほかの業界でいえば、社員数が30人以下の零細企業と大差ないのだという。「まじめに仕事をするほどにむなしくなる」と5人は話していた。
たとえば、廃刊となったこの雑誌編集部では数年前、ある編集者が副編集長(課長級)の経験がないのに、編集長(部長級)になったという。通常、こんな昇格はありえないはずだ。ところが、「抜擢人事」として断交されたそうだ。「使える編集長」を起用し続けたが、その多くが「使えない編集長」とレッテルをはられ、職を離れていたという。
販売不振の起死回生策として、副編集長の経験がない編集者を編集長にしたのだが、案の定、破たんしたらしい。その編集長は経験不足のために、部下である副編集長をはじめ、7人前後の編集者を自らが意図したように動かすことができないようだった。結局、編集長という権力で動かすようになる。ときに強く当たり、ときには大きな声でしかりつける。このことに不満をもった編集者数人が企業内労組に「編集長からのパワハラに遭っている」と訴えたそうだ。
企業内労組の役員が、編集長の上にいる役員などに「組合員(訴えた編集者のこと)から苦情が来た」と伝えた。すると、役員は編集長にそのことを話し、労組に訴えた編集者数人と編集長などを含め、関係者10人ほどで解決に向けての話し合いをした。「パワハラ」は「双方のコミュニケーション不足」で生じたものであり、「編集長にその意識はない」という結論になったのだという。その後の人事異動で関係者たちの一部は、他部署へ異動となったようだ。
この一連の騒動は、関係者の間ではかん口令がしかれ、タブーになったままだという。退職者5人のうちの数人は、「役員は、社外の労組(ユニオン)などに話を持ち出されないようにするための懐柔策として話し合いの場を設け、そこで不満分子の編集者にガス(不満)抜きをさせた。その後、人事異動で態勢をシャッフルし、すべてをシークレットにした」と話す。
私の取材経験をもとにいえば、「パワハラ」はする側、される側それぞれの認識に大きな差があり、どちらの言い分が正しいのか、正確に判断することは難しい。仮に、この一連の騒動がすべて事実であるとすると、20~30代で意識の高い編集者はやり切れぬ思いになるのではないだろうか。このほかにも、この出版社の人事のあり方には、話を聞く限りでは首を傾げたくなることが多々あった。おそらく、廃刊となった雑誌の編集者たちがベンチャー企業にあそこまで感化され、称え続けたのは、自らが勤務する会社の旧態依然とした人事のあり方に嫌気がさしていたからではないか、と私は思うのだ。
通常、会社員の多くは、人事評価や育成、配置転換、昇進・昇格に異議を申し立てることはなかなかできない。この雑誌の編集者たちも同じく、言えなかったのだろう。そのようなときに、ベンチャー企業をわずかながら取材し、そこが自分たちのうっ積した不満がまったくないような職場に見えたのではないか、と思う。実は、人事制度や賃金制度は未熟で、人事評価や育成、配置転換などに深刻な問題を抱え込んでいるのだが、そのことに気がつかなかったのだろう。そのような思いでベンチャー企業を取材し、記事にしていたのならば、売れなくなるのは無理もない。
今回のことは、あくまで私が元退職者たちから聞いたものである。現役の社員に連絡をしても、ここまでは答えなかった。私が強調したいのは、何かの商品や製品、サービスが売れなくなるとき、そこには社内の人事にきしみが生じていることが多いことだ。それらを販売しないようにしたところで、問題は残り続けるのではないだろうか。
![]()
![]()

▲「WEDGE Infinity」の新着記事などをお届けしています。