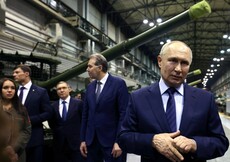「何か声を掛けられてもパニックになっているので『わからん、わからん、体がうごかへん』としか言えませんでした」
その後、救急車の中で服を切って脱がされて麻酔を打たれた。
目が覚めたときはICUの中だった。ベッドを囲むように家族や恩師がいた。人工呼吸器のため言葉が出なかった三阪は、看護士が差し出した五十音ボードを使って「ごめん」と指差した。心遣いの細やかな三阪は、迷惑を掛けたことを詫びたかったのである。
「何をどう頑張ったらいいんだ」
6月21日、頸椎の手術が行われた。その日は三阪の18回目の誕生日だった。
それからの3カ月半は寝たきりの生活になった。徐々に手の麻痺が取れて少しずつ動かせるようになったものの、当たり前に出来ていたことが出来なくなったことの現実を様々な思いとともに理解していった。
 事故当時の心境について語ってくれた三阪さん
事故当時の心境について語ってくれた三阪さん(撮影:編集部)
「寝たきりの期間、自分がどんな感情でおったんかはよくわかりません。ただ、とてつもなく大変なことが起きていることはわかりました。悲しい、悔しい、つらいという感情を通り越して、生きているのかさえもよくわからない状況だったと思います」
この頃、お見舞いに来た人たちに「頑張って」と声を掛けられた。悪気などあろうはずがない。みんな励ましたいという思いから出た言葉だったはずだ。
しかし「思うように体も動かないし寝返りを打つことさえも出来ません。看護士さんに『左に向けますね』『起こしますね』と体を動かしてもらわなければならないし、水を飲むにもナースコールを押して頼んでいました。この状態で何をどう頑張ったらいいんだ」という思いに苦しめられ、人に会うのが怖くなった。
極めつけは同級生の存在だった。健康的に日焼けした真夏の彼らとは対照的に、三阪の顔は白くなるばかり。「本来なら、僕もそこにいるはずなのに……」
三阪の望みで家族以外は面会謝絶となった。家族になら苛立ちや、内面に燻る思いをぶつけることができた。
車いすラグビーとの出合い
手術後、3カ月半が過ぎ、脊髄損傷者のリハビリに定評のある病院に転院が決まった。元に戻れば留年してでも、もう一度『花園』を目指してチャレンジできる。