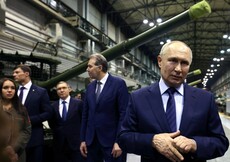年末の少し浮かれた慌ただしさの中、パラダイムを一転させるような科学的発見の難しさと危うさ、そして、そこへ至る、あるいは至ることのできない研究者たちにとってのパートナーシップの役割や捏造への誘惑など、本論を少々脱線して思いを馳せてしまいました。
遺伝子研究の過去について語る、著者の冷めた眼差し
 『双子の遺伝子――「エピジェネティクス」が2人の運命を分ける』(ティム・スペクター 著、 野中香方子 翻訳)、ダイヤモンド社)
『双子の遺伝子――「エピジェネティクス」が2人の運命を分ける』(ティム・スペクター 著、 野中香方子 翻訳)、ダイヤモンド社)
さてさて、『双子の遺伝子』は、「遺伝は遺伝子だけでは決まらない」とするエピジェネティクスの概念を、豊富な双子研究の事例を通じて解説したもの。2章以降のタイトルは、才能遺伝子、肥満遺伝子、浮気遺伝子、同性愛遺伝子など、それぞれが週刊誌の見出しになりうる存在感ですが、読者はこの本にちりばめられた予想外で目をひく双子のエピソードばかりに心を奪われていてはいけません。この本の真の価値は、序章と1章で、カンメラーのエピソードを含む100年ちょっとの遺伝子研究の過去について語る、著者の冷めた眼差しの中にあります。
インチキ科学者とされたカンメラーは、その後、エピジェネティクスの登場で再評価を受けます。エピジェネティクスの趣旨は、環境が同じで遺伝子が同じでも結果が同じであることは稀で、「遺伝子には確実性がない」ということ。同じ遺伝子を持った一卵性の双子が、片方は病気なのに片方は健康だったり、片方はゲイなのに片方はストレートだったりするように。
ここでカンメラーの件のタネ明かしをすれば、サンバガエルの実験は再現されなくてもよいということになる。そして、後になって、捏造したのはカンメラーの方ではなく、実はナチス支持者が増え始めた当時のウイーンで、優生学的な思想の遺伝学者が、社会主義者としても有名だったカンメラーを陥れるため標本に墨を打ち込んで改ざんを加えたのだ、という説も出てきました。
本書では、STAP問題に似たカンメラーの騒動のほか、旧ソビエト連邦における衝撃の過去も語られます。
1928年、小麦を低温処理して生産性をあげる「春化処理」を考案したソ連のルイセンコ。農民出身で高等教育を受けていないこの男は、環境さえ整えば遺伝条件に関わらず生物は能力を上げることができるのだという主張で遺伝子絶対論を否定し、貧しい農民でも科学者になれるという出自も共産党の宣伝向きだとスターリンに重用されました。