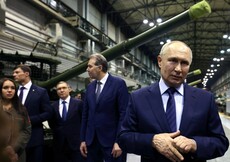香港には「秦城に愛心を寄せる」という運動が続いている。秦城とは、北京にある主に政治犯が収容される監獄である。失踪、連絡断絶、無実の投獄などによって人権や民主を求めた人々が運び込まれる先の秦城監獄を一つの象徴として、彼らを支援しようという運動である。
天安門事件への追悼と抗議
そんな中国の人権や政治への香港の関わり方は、中国を祖国と見なす態度から来るものであり、昨今の脱中国化が進んだ台湾では考えられない運動だった。天安門事件への追悼と抗議は、香港人にとって中国人である証明だったと言える。
中国政府は、香港で天安門事件を批判する民主派を忌避し、懸命に親中勢力の育成に力を注いできたのだが、実は、中国にとって、こうした民主派による中国批判もまた、中国に対する一種の連帯意識の発露であり、香港における一国二制度の安定にとって一定の存在意義があったことを、「中国の民主は他人事だ」と言い切る香港の本土派の登場によって、改めて噛み締めるときが来るのではないだろうか。
香港人は中国の民主化に期待した。97年に英国から返還されるときも、自分たちが中国の民主化に貢献できれば、中国が民主的な社会になり、いつか香港とも一国二制度の必要がなくなる―—。それが香港における民主派の思想的なバックボーンであり、我々外部の人間も「香港が変える中国」を期待していた。しかし、今日の中国において、民主は前進する兆しはなく、むしろ後退の一途をたどっているようにすら見える。16日に初めて当事者の一人が口を開いた香港の書店関係者の不可解な拘束問題などに象徴されるように、香港が中国を変えることはなく、香港は中国に変えられる一方に見える。そんななかでは、「中国が民主化すれば、香港の民主も守られる」という民主派のロジックは風前の灯火になっている。
天安門事件の記憶が薄れ、「六四記念館」の存在が風化するとすれば、それは「香港式愛国」の終焉であり、香港と中国との絆が風化することに等しい。それは、ある意味で、天安門事件が批判され続けるよりも、中国にとっては本質的に好ましくないことである。香港人を天安門事件に引き戻すにはどうすればいいか。そんな矛盾した問いをいまの中国は香港で突きつけられている。記念館の展示は、そんなことを私に感じさせた。
![]()
![]()
![]()
▲「WEDGE Infinity」の新着記事などをお届けしています。