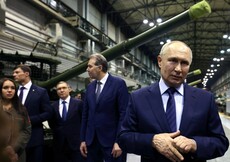冒頭に問われるのは、1966年、母と妻を殺してからテキサス大学タワーに上り、無差別銃撃で46人を死傷させた男の事件。男は警察に射殺されたが、以前は平凡な私生活を送っており、「自分の脳に変化が起こっていないか究明するために検視解剖をしてほしい」と遺書に記していた。
解剖の結果、彼の脳に腫瘍が見つかり、扁桃体を圧迫していたことがわかった。扁桃体の損傷は、感情と社会性の混乱を引き起こすといわれる。
さて、この場合、彼の無分別な殺人に対するあなたの気持ちは変わっただろうか? 彼が生きていたら、量刑を加減することになるだろうか? 運悪く腫瘍ができて、自分の行動を制御できなくなる可能性は、あなたにだってあるのでは?
<脳に腫瘍を抱えてタワーに上った男性のことを考えると、私たちは非難に値するかという疑問の核心に触れることになる。法律用語で言えば、彼は『有責』なのか? 自分には選択の余地がない脳の損傷を受けている場合、その人にどの程度責任があるのか? なにしろ、私たちは自分の生体と無関係ではいられない。そうでしょう?>
著者の問いかけは、脳を探る技術が向上するにつれ、広く、重くなっている。
腫瘍のせいで突発的に小児性愛になった男性、万引きなどの脱抑制行動を止められなくなる前頭側頭認知症の患者、治療薬の作用でギャンブル依存になるパーキンソン病患者、殺人夢遊病患者の例などが挙げられており、容易に答えの出る問いではないと気づかされる。
そこで著者は、本書の前半で見てきた脳に関する新たな理解――自由意志はたとえ存在するにしても、巨大な自動化されたメカニズムのうえに乗っている小さな因子にすぎない――という理解から、犯罪の有責性を問うことは意味がない、と訴える。
現在の刑罰スタイルは、個人の意思と責任を土台にしているが、有責性は現在の技術の限界で決まることになり、筋が通らない、という意見には、たしかにうなずける。
「脳に適した前向きな法制度」として、著者は、「生物学的な理解を活用した更生のカスタマイズ」を提唱する。最新の脳画像技術を用いて、衝動を抑制するように脳を訓練するという具体的手法も提案している。
「神経法学」という新しい分野に軸足を置き、ベイラー医科大学では「脳神経科学・法律イニシアチブ」を主宰する著者ならではの、斬新だが、説得力のある主張である。
神経生物学者、法学者、倫理学者、政策立案者を巻き込んで、神経科学の新たな発見を法律や刑罰、更生にどう活かせるかを研究するプロジェクトとのことだ。アメリカのみならず、日本でも大いに参考にすべき考え方であると思う。
![]()
![]()

▲「WEDGE Infinity」の新着記事などをお届けしています。