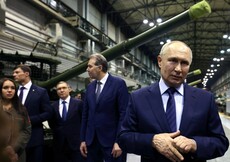日本VSボリビア
両国の幸福を測る項目のうち、アマゾンの村を再訪する前に、気がついていた目立った相違点は3つある。
地縁・血縁
国連調査の社会的支援(困ったときに頼ることができる親戚や友人がいるか)に相当する。
筆者は日本でホームレス、自殺未遂者、殺人事件などを取材してきたが、「寄る辺ない」という言葉をよく聞いた。とりわけ郊外に住むサラリーマンは地縁がない。親戚や友人は遠方に住み、簡単には会えない。何か問題が起こると、家族(妻)に過度の負担がかかる。縁が少ないと、最後に頼るのは行政機関である。だが行政はしばしば恣意的な対応となる。生活保護を受けられずに自殺するなど、全く救われないこともある。
一方、アマゾンの小村は狭く、傍らに友人や血縁や名付け親や恋人がいる。クモの巣のようにセーフティネットが張りめぐらされている。
利便性
おそらく日本は世界一便利である。けれどもコンビニやウォシュレットに代表される日本の利便性は、生きる実感を乏しくさせる罠のひとつともいえる。さらに、ヤマト運輸に見られるように消費者の利便性を極大にするためには、それを実行する労働者に過度の負担を強いることになる。利便性は、もろ刃の剣である。電気がないから幸せだとさえ言える(「日本人はなぜやめた? アマゾンに残る夜這いの文化」参照)。
時間―スローライフ
ボリビアのスローライフの象徴は列車だった。当時ブラジル国境と大都市のサンタクルスを繋ぐ列車は、1日遅れ、2日遅れということも珍しくなかった。どこかで脱線し復旧に遅れているからだった。1時間遅れで列車が到着すると、イライラするどころか、「ラッキー、時間どおりだ」と幸運を感じるようになった。
しかし、これ以上に大切な幸せの源泉があったのである。
不快感にこそ幸せのヒントがあった
20数年という星霜を経て、村を訪れ、友人たちの消息を尋ねた。村を出る当日に、子供たちと、滝壺に遊びに行き、夜には子供の親でもある友人のクッシ―と会った。因縁のある男で、ある意味会いたくなかった。
彼は当時食堂の助手として働いていたが、遅刻が多く、素行も悪かった。しかも性病にかかり、何日か仕事を休んだ。食堂の責任者の依頼もあって解雇の手続きをした。だが、彼は当時筆者が付き合いのあった女性の義理の兄だった。
ある夜、クッシーはディスコの前で「なんでおれを首にするんだ!」と殴り掛かってきた。だが、彼は小柄だった。足をかけて押し倒し、逆に殴りつけた。苦い思い出である。
そのクッシーは彼の家の庭の椅子に座って妻といっしょに待っていた。筆者を見るなり言った。
「なんだ、随分年取ったな。ひげが白いじゃないか」
彼とは同年だった。
「ああ、苦労しているからな」
「いま、ベネズエラにいるんだって」
「うん、そうだよ。まもなく日本に帰る」
彼は、道路掃除の仕事をしていると言った。子供は5人だ。12歳の少年のあだ名は、トウキョウである。
列車が来る前に村に一軒しかない雑貨屋でビールを何本も購入し、外で飲んだ。近況を語り、当時の思い出に浸った。筆者には殴り合った記憶が棘のように心に刺さっていた。
列車が来たので腰を上げた。クッシーが言った。
「なあ、ちょっと金をくれよ」
彼は何ら悪びれる様子も見せずに金をせびってきた。普通はせびることに苦痛を感じるはずだが、そのような様子はまったくない。せびられるほうが苦痛なだけだ。カーニバルのときに流行した陽気な歌にこんなのがあった。
もう金を貸してくれなんていうなよ。これが最後だから、もう2度と顔を見せないでくれ!
アマゾンの友人は再び苦い思いを筆者に抱かせた。持つ者と、持たざる者、それを彼は意識させる種類の人間だった。けれども視点を変えるとそれも微妙だった。彼は大きな庭のある家を持って、子供を5人も育てている。
しかもボリビアには「Okinawa」と「San Juan」という日本人移住地が2つもある。戦後の貧しい日本から多くの移民を受け入れてくれたのだ。今だって、筆者を含め、援助や投資の名目で日本人や日本企業が進出する。裕福ならば国内に留まっているはずだ。
迷ったが、求められるままに彼に金を手渡した。不快だ。くさくさした気分だ。2度と会わないと決め、列車に乗り村を離れた。