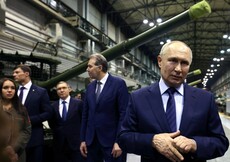2020年12月、カンサスで郡保安局警察官が、非武装の黒人男性をパトロールトラックで追い詰め、意図的にひくという信じがたいビデオ映像が公開された。映像には車輪の下になって倒れている黒人男性に、白人の警官3人が銃を向けながら近づいていく姿が映されている。
被害者自身、退職したばかりの元警官で、ハイウェイを運転中に職務尋問で止められたという。最初は免許証の提示など普通に応じていたが、さらに3台のパトカーが現れて周りを囲まれたこと、目撃者もいない郊外で夜間だったため、命の危険を感じて徒歩で逃亡したという。
元警官の黒人が、白人警官に囲まれて「何をされるかわからない」と身の危険を感じた、というところに、この国の人種差別問題の根深さを感じずにはいられない。
「白人の彼女がいるって本当?」
2000年の国勢調査によると、筆者が高校時代を過ごしたノースカロライナ州の黒人人口は全体のおよそ21%だという。全米の州の中で、黒人人口の比率は8番目に多い。ノースカロライナはかつて綿花とタバコの栽培で栄えていた土地で、これらの黒人の大多数はプランテーションで労働していた奴隷の子孫に違いない。
だが筆者の通っていた私立高校では、全生徒100人中黒人はたった1人しかいなかった。
ダグという名前の、すらっとした長身の男の子だった。なぜダグがこの学校を選んだのか、わからない。公立学校のレベル、環境に不満だったのか。差別されることを、心配しなかったのか。でも筆者は、一学年上だった彼と言葉を交わす機会はなかった。

ある日、体育館で体育の授業を終えて一息ついていたときのこと。片隅のバスケットボールのコートで一人黙々と、ダグがシュートの練習をしていた。
トントン、とドリブルしてはシュートを繰り返すダグの周りを、気が付いたら体育の授業を終えたクラスの女子たちがぐるりと取り囲んでいた。
「ねえダグ、聞きたいことがあるの」口火をきったのは、ちょっとこまっしゃくれたマルセーユという女の子だった。
「何かな?」
「あなた、白人のガールフレンドがいるって聞いたけど、本当?」
「そうだよ」
「ウソばっかり」
「ウソじゃないよ」
「じゃあ、彼女の名前は?」
「ウェンディ」
「あははは、その名前、今考えたんでしょ」
マルセーユの周りにいた女の子たち数人も、声を揃えて嘲笑った。
「違うよ」
ダグは、こんなことは慣れているといった様子で、淡々と受け答えた。
視線をゴールから一度もそらさずシュートを続けていたけれど、やはり居心地悪くなったのだろう。しばらくするとボールを小脇にかかえ、黙って体育館を後にした。
「黒人はジャングルを走る人たち」
英語も不自由しなくなった現在の筆者なら、迷うことなく女の子たちを一喝して説教の一つもかましただろう。
だが当時まだ15歳だった筆者は、モヤモヤした気持ちを抱えながらも口を出すことなく黙って見ていた。それまで日本で普通に暮らして、「人種差別はいけないこと」と教えられて育った。でも日本の地方都市では、「人種差別」というのがどのような形で現れるのか、肌で実感する機会はそれまでなかった。
「ジェニー、聞きたいことがあるの」
女の子たちが一人二人といなくなった後、筆者はグループの中で比較的大人しいジェニーという女の子にそう声をかけた。ブルネットに青い目のジェニーは、英語の不自由な留学生に対しても、辛抱強く相手をしてくれる少数派の温和な同級生だった。
「あなたたちは、どうして黒人を差別するの?」
当時の英語力では、湾曲な表現などできるはずもなく、こう直球を投げるのが精いっぱいだった。ジェニーは、少しも驚いた様子を見せずに、大人が子供に言い聞かせるように、ゆっくりこう説明してくれた。
「あのね、黒人たちはついこの前までジャングルの中を裸足で走り回っていた人たちなの。私たちよりも遅れているから、差別されても仕方ないのよ」
その彼らを故国から拉致して、鎖につないで連れてきたのはあんたらの祖先だろう。と言いたかったが、悲しいかな、英語が思うように口から出てこない。ジェニーの、悪気のない透き通るような青い目を見て、筆者は黙り込んでしまった。