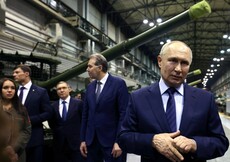聞き手/構成・編集部(川崎隆司)

神奈川大学法学部、東京女子医科大学看護短期大学卒業。国立感染症研究所実地疫学専門家養成コース(FETP)修了。聖路加看護大学助教、国立国際医療研究センター感染症対策専門職などを経て現職。国立国際医療研究センター国際診療部客員研究員。
吉峯耕平 Kohei Yoshimine弁護士
田辺総合法律事務所弁護士。東京大学経済学部卒業。日本医事法学会、一般社団法人日本医療情報学会、デジタル・フォレンジック研究会などに所属。第一東京弁護士会総合法律研究所IT法研究部会前部会長、国立国際医療研究センター臨床倫理委員会委員、司法改革推進センター委員などに就任。
編集部(以下、──)9月末をもって全都道府県で緊急事態宣言およびまん延防止等重点措置が全面解除された。新型コロナウイルス対策の近況は。
堀 新型コロナの特性自体はある程度早い時期から把握できていたが、ここにきて医療現場レベルで〝闘える武器〟が揃いつつある。ワクチンの効果で重症患者が減少したのに加え、軽症・中等症患者へは中和抗体薬「ロナプリーブ」の点滴投与(抗体カクテル療法)によって症状悪化を抑える効果が見込める。さらに、現在承認申請中の経口治療薬が年内を目途に行き渡れば、いよいよ長かったウイルスとの闘いの勝利に向けた一筋の光が見えてくる。
吉峯 素人目には「ワクチンができるまで数年はかかるのでは」と思われたが、世界中が総力を挙げたことで1年足らずで完成にこぎつけた。さらに、従来のワクチンの常識と比べ有効性が高く、副作用もほとんどないと聞く。国内の接種率もかなり高くなっており、この点はしっかりと評価すべきだ。
堀 ウイルスとの闘いのフェーズが移行する今だからこそ、われわれもコロナに関する混乱を早期に整理し、これまでの仕組みをモデルチェンジしていくべき時期にある。
──具体的には、どのようなことを見直していくべきか。
堀 例えば、感染拡大初期に「濃厚接触者に対しては患者と接触した日から起算して14日間は自宅待機を要請するように」という厚生労働省の方針が示されたが、ワクチン接種者や、軽症の自宅療養者の家族に対してまで2週間の自宅待機を強いるのは過剰な対応だ。検査を併用することで短縮でき、感染データを踏まえて待機期間を見直す国も増えている。日本でも、新型インフルエンザ等対策特別措置法の第5条に「国民の自由と権利に制限が加えられるときであっても、その制限は当該新型インフルエンザ等対策を実施するため必要最小限のものでなければならない」という法に基づき、自宅待機期間の見直しを図るべきだ。
吉峯 法律の枠を逸脱した対策でいえば、感染症法では、感染者は入院させるしか選択肢がなく、自宅療養や宿泊療養は、本来認められていなかった。
歴史を紐解けば、ハンセン病患者への不必要な長期間の隔離を違法とする裁判例があり、感染症法が改正されて、隔離の概念をなくしてしまった。陽性者に対する強制措置は「入院勧告」しか用意されていない。〝隔離〟ではなく入院と医療ケアによる〝保護〟だという建前で、結果的に隔離が達成されるという欺瞞的な法律だ。一方、新型コロナは、無症状・軽症の陽性者から感染が広がるのが特徴で、医療機関以外での隔離(自宅療養、宿泊療養)といった法的根拠なき身柄拘束を実施せざるを得ず、人権侵害として極めて問題だった。法律に基づかないことで「自治体がどうやって支援するか」「誰の負担でどこまでの治療行為を行ってよいか」など、さまざまな問題が曖昧になったままだ。また、法律の裏付けがなければ、予算、人員、行動計画、どの程度の検査が必要かといった体制を事前に整備することができず、泥縄式の対応になってしまう。
新型コロナは予想外の感染症なので、発生当初は根拠がない中で対応するのもやむを得なかったかもしれない。しかし、これだけ時間が経っているのに、立法措置がほとんどなされていないことは、諸外国と比べても理解できない。隔離が法律に書いていないなどという非常識な欠陥を見直し、現実的な対応ができるよう法改正すべきだ。