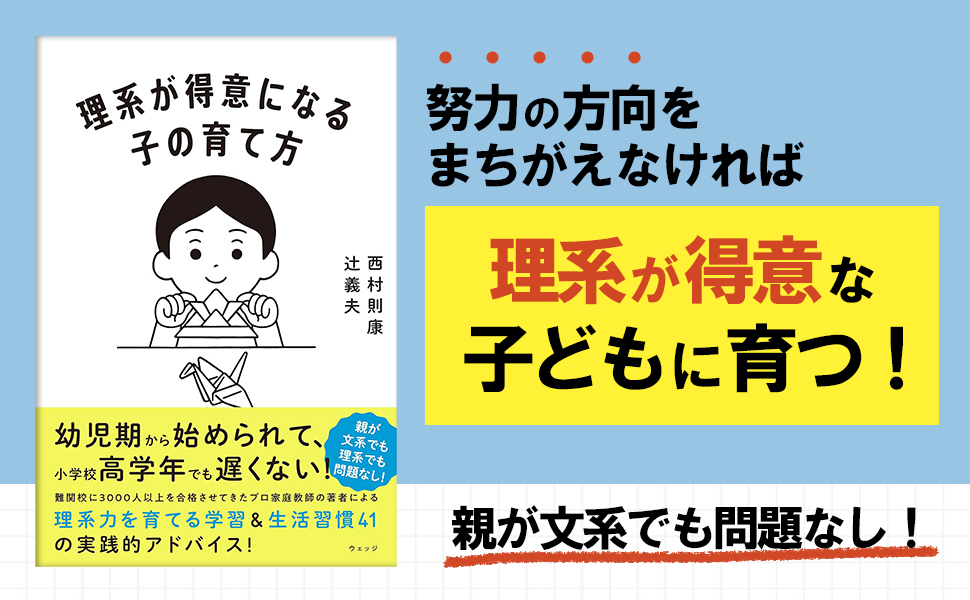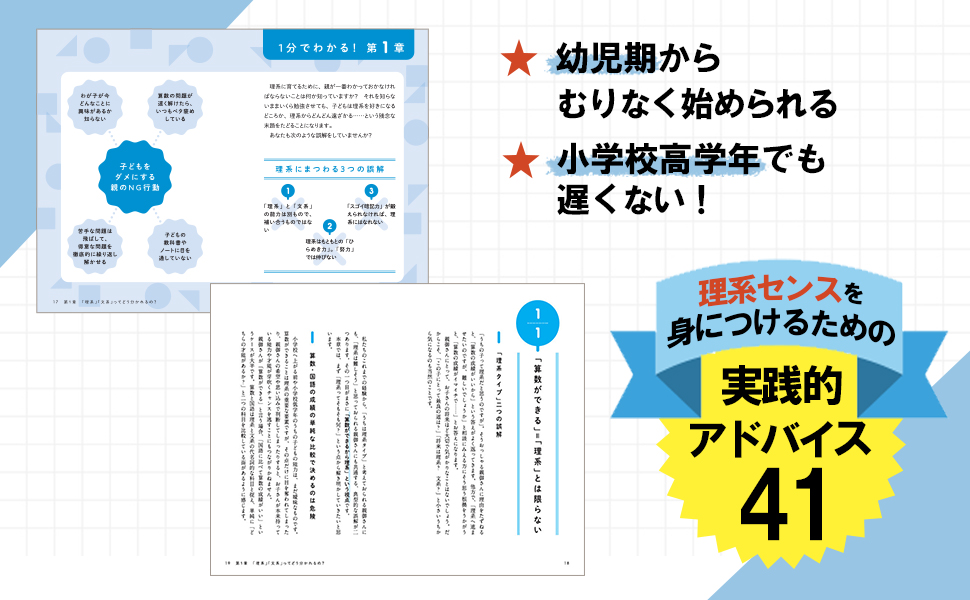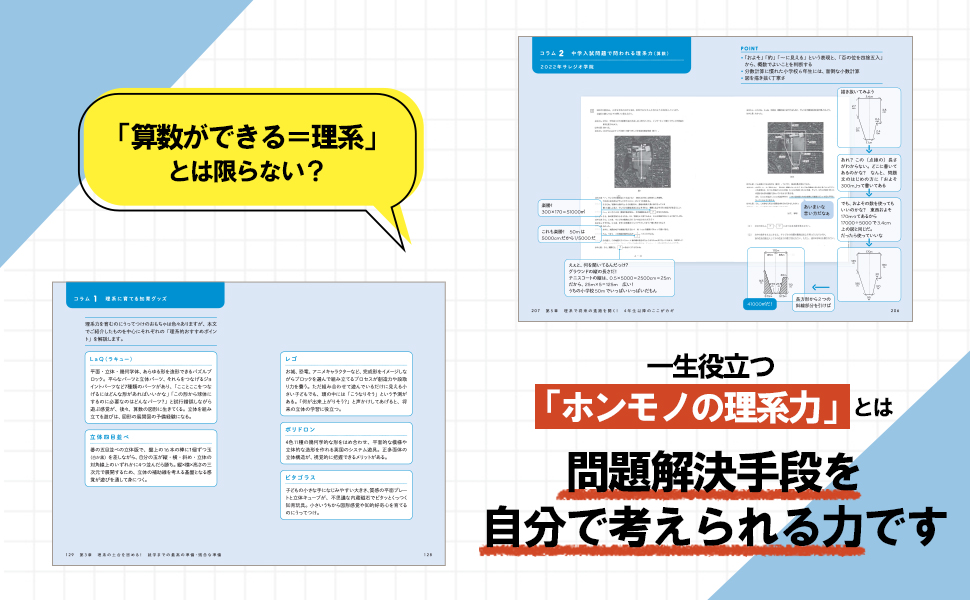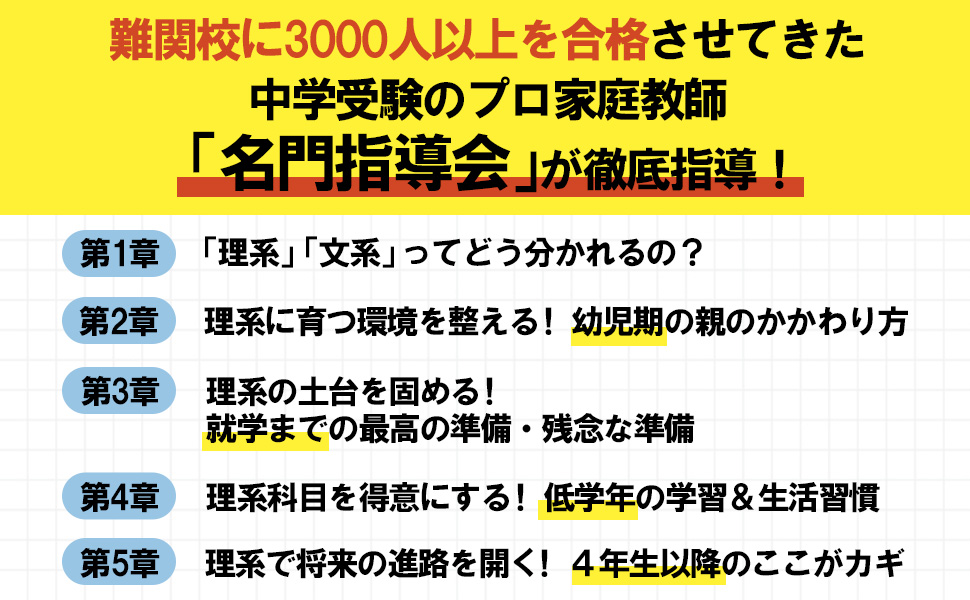<好評2刷>(2024年2月)
◎幼児期から始められて、小学校高学年でも遅くない!
理系が得意になる学習&生活習慣・41の実践的アドバイス!
「算数ができる=理系」とは限らない?単純な判断は子どもの可能性を狭めてしまう!
令和の時代に必要な「理系力」を親が理解し、子どもの可能性を無限に広げよう
「わが子を理系にしたい」――。先が見えない時代を生き抜くために、
子どもには「専門的な能力を身につけてほしい」と考える親御さんが増えています。
その中で、「理系」という選択肢が頭に浮かぶのでしょう。
しかし、「家庭でできることはあるのでしょうか?」「親が文系なので自信がなくて……」
という不安な気持ちが先行し、子どもに「間違った方向」で努力をさせてしまうと、むしろ算数・理科嫌いになりかねません。
理系力を育てるための学習・生活習慣は、幼児期から始められて、小学校高学年から取り組んでも遅くありません。
単に学力が高いだけではなく、目標に向かう方法や問題解決手段を自分で考えられる
「ホンモノの理系力」を養うため、子どもの可能性を最大限引き出す方法をお伝えします。
<本書の目次>
第1章 「理系」「文系」ってどう分かれるの?
1-1 「算数ができる」=「理系」とは限らない
「理系タイプ」二つの誤解
算数・国語の成績の単純な比較で決めるのは危険
理系も文系も伸ばす「論理的思考力」
1-2 「理系力」を下支えする「大切なもの」とは
文章問題を読まずに解く子!?
算数のお悩みナンバー1
「理系的な読み方」を身につけるために
1-3 「暗記ベース」の学習が理系を遠ざける
丸暗記は理系力の敵
「どうしてその式で解けるの?」と聞いてあげる
「たくさん、速く!」より「考えながら、ゆっくり」
1-4 理科嫌いになる学年はだいたい共通している
理科は暗記科目と思い込んでいませんか?
理科好きな子が陥りがちな落とし穴
1-5 本当はどんな子でも理系に強い子に育てることができる
ある程度の年齢まではバランスよく
「理系」or「文系」のチェックポイント
親のかかわり方しだいで変わっていく年代
1-6 将来を見据え、伸ばしておいて損はないのが「理系力」
将来の学力を盤石にするために
理系力という「一生もの」の力
1-7 理系に育てるロードマップ
成長段階に合わせて気をつけたいポイント!
これから始めても間に合う!
第2章 理系に育つ環境を整える! 幼児期の親のかかわり方
2-1 学力のベースは「なごやかな親子関係」にある
親子で「ご機嫌」に過ごすことが一番大切
将来伸び悩む子が見せがちなある素振り
親子の会話で論理的思考力が高まる
2-2 「理系的思考」の始まり「なぜ?」を育てる
子どもの「なぜ?」は賢くなるチャンス
正解を教えようとしなくても大丈夫
親の声かけが子どもを伸ばす
2-3 好きなことに熱中する体験をたくさん
謎の行動こそゆったり見守り、観察
「夢中」に潜む理学的発想、工学的発想
2-4 一緒に遊ぶだけで子どもは真似して賢くなる
模倣は学びの基本
生活にないことは真似できない
中学受験期の親御さんは趣味の継続を
2-5 おやつのあげ方にも理系に育てるコツがある
教えようとすると子どもは敏感に察します
理系に育てたいなら「なぜなんだろうね?」
むしろ子どもに教えてもらうスタンスで
第3章 理系の土台を固める! 就学までの最高の準備・残念な準備
3-1 まずは指を使って一緒に10数える
数の数え上げは暗唱するように
10を超えたら歯抜け状態でもどんどん先へ
数え方のバリエーションで遊ぶ
3-2 少しでも早く身につけたい二つの「数の感覚」
数の「順番」の理解は簡単ではない
意識して育てたい「個数」の感覚
「個数」=ボリューム感=量感
3-3 ペーパー学習の繰り返しだけでは数の「量感」は育たない
プカプカ浮くアヒルが教えてくれること
「○っていう数はだいたいこれくらい」という大切な感覚
数えるのが得意なのと、個数の感覚が育っているかは別もの
3-4 5歳までに「10のかたまり」を徹底的に
「10の補数」の理解こそ幼少期の最大ミッション
ブレイクスルー体験のない4年生の悲惨さ……
3-5 1年生の算数が盤石になる「実物遊び」
小銭を使って駄菓子屋さんごっこ
「1個」と「5円」の違いがわからないワケ
家にあるものをご家庭なりに工夫して
3-6 言葉の理解が広がれば数の苦手意識は小さくなる
リンゴがナシに替わると文章問題が解けない!?
引くと書いてないけど「引き算」だとわかる感覚
小さいうちから実物と名詞を対応させる
3-7 リンゴを丸に置き換えるイメージ思考の大切さ
言葉の理解の先にある「抽象化」という知力
ドリル学習にひと手間かける
3-8 「△探し」「○探し」遊びが図形感覚の発達につながる
図形の名前を日常で「聞かせる」
どんな物がどんな形?
間違い探しは語彙を増やせて一石二鳥
3-9 折り紙でまずは平面図形に親しむ
図形の感覚は身体感覚
自由に折って、一部を切り落としてみる
高学年でも図形でつまずいたら折り紙を
3-10 高い所から見下ろす体験で空間把握力アップ
立体図形の学習は屋外で
かくれんぼと積み木の深い関係
平面から立体へ感覚は育つ
コラム1 理系に育てる知育グッズ
3-11 重っ!軽っ!熱っ!冷たっ! 感覚の記憶をたっぷりと
「風が吹いてるね」と声をかけるだけでいい
「感覚の記憶」が理系力には欠かせない
重量、温度、質感の豊かな体験を
3-12 デジタルデバイスは「わが家のルール」を決めて活用
一人で操作可能になってからの時間管理が重要
タブレットの拡大機能は生物の学習向き
ポジティブな面はしっかり見せる
第4章 理系科目を得意にする! 低学年の学習&生活習慣
4-1 1年生は「一つの計算が正確にできる」が目標
遊びの数と机の前の勉強が近づいてくる時期
子どもは「大体合っていればいい」と思っている
「勉強のルール」を知るところから勉強は始まる
4-2 基礎的な計算力が身につく毎日の学習量とは
教科書準拠の問題集を2冊ずつ買う
学年ごとの「計算のルール」を確実に積み重ねる
中学受験する場合は3年生からギアチェンジ
4-3 九九を全部言えても九九表は張っておく
算数が苦手な子の「九九あるある」
数字だけより絵がある九九表を選ぶ
時間をかけて醸成していく
4-4 最初の関門「二桁の割り算」をクリアする
二桁の割り算が最初のつまずきポイント
「数を丸める」を支える感覚とは
4-5 「どうしたらラクに計算できるか」が算数好きへの入り口
「25×4=100ってめっちゃ便利!」
計算の作法に則った「ルール」を活用できる子は強い
算数好きには「マイルール」がある
4-6 単位は「1cm」を体感することから始める
子どものからだのパーツを測ってあげる
100倍、1000倍という単位の仕組み
勉強しながら記憶を強化
4-7 理系センスを磨くお手伝い習慣
体積は子どもが実感しづらい
水回りの遊びで単位との距離がぐんぐん縮まる
「スケルトン卵作り」で実験遊び
4-8 手を動かし、試行錯誤を楽しむ
実験教室はリトマス試験紙として
コンパスを使えない理系大学生!?
実験キット、体験学習も活用
4-9 「算数苦手だね」「理科嫌いなの?」は絶対に口にしない
親子の連携という環境づくり
先回りして子どもの失敗を占わない
大人の会話に子どもを交える
第5章 理系で将来の進路を開く! 4年生以降のここがカギ
5-1 「理系の芽」が見えてくる10歳前後
子どもの世界がガラッと変わる年代
理系に向く子の思考傾向
「納得感」が学力の源となる
5-2 「納得感」のある学習の積み重ねで理系力を伸ばす
基礎的な計算学習は毎日10分から15分
学力が不安定な子の「わかったつもり」
最上級の「わかった」が揺るがない自信になる
5-3 図や式をしっかり書いて解く習慣が理系には必須
得意だった理系が高学年で下降を始める理由
フリーハンドで描く練習を
「頭の中で計算できるもん」がアブナイ
コラム2 中学入試問題で問われる理系力(算数)
5-4 理科の実験で学びを10倍にする
実験をただの作業で終わらせない
自由研究、読書感想文などにも共通の「思考5点セット」
コラム3 中学入試問題で問われる理系力(理科)
5-5 理系親が得意を生かすコツ、文系親がうまく並走するコツ
理系出身に多い「方程式父さん」
勉強熱心だった方がなりがちな「満点解答母さん」
見直しのネガティブなイメージを払う方法
5-6 備わっている文系力を生かしつつ、理系力もアップさせる
「文系と比べると理系ができない」という悩み
「言葉の理解」を深める工夫を継続
将来の進路選択までにできること
5-7 将来の高校・大学進学で理系の道を選んでいくために
公立中学、公立高校で理系力を伸ばす勉強法
理系をあきらめて文系にするきっかけは二つ
数学で挫折しない独学法
5-8 「自分は大切な存在だ」という自己肯定感が学力のベース
成績が落ちても折れない子の秘密
「あなたはがんばれる子だよ!」を繰り返し伝える
思春期に入っても「見ているよ」のスタンスで