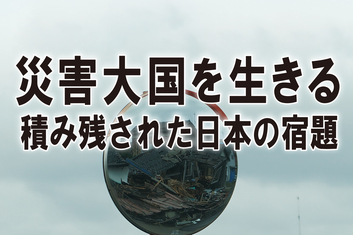「私は明治天皇の生まれ変わりだ」と嘯くドイツ系移民の陸軍中将アルフレド・ストロエスネルは、1954年にクーデターで大統領に就任して以来、憲法条項の大統領任期を何度も修正し、89年まで35年間もパラグアイに君臨した。独裁者の在任中にどんな国かと行ってみると、旅行者には桃源郷のような素晴らしい国だった。だが、翌年宮殿クーデターが起こり、彼は追放されてしまう。その原因は大きな声では言えないし、書くのもおこがましいものだった。そして2017年再び独裁につながる憲法改正が上院で可決されてしまう。国民は意外な方法で下院での可決を押しとどめ、独裁を拒否した。

まるで日本の田舎のような
88年の8月、国境を越えると別世界だった。車窓には緑の農耕地が広がりブラジルやボリビアの低地よりも開拓が進んでいた。車窓を椰子の木々、ラパチョの艶やかなピンクの花々(日本では癌などに対する民間療法の紫イぺとして知られる)、牛、小さな集落、イエズス会師が建てた古い教会等々が通り過ぎて行く。アルゼンチンやチリに見られるスラムは首都のアスンシオンに着くまで、ついぞ見かけることはなかった。
筆者はアルゼンチンのポサーダとパラグアイの国境を越えて、乗り合いバスで6時間ほどの距離にあるアスンシオンを目指していた。
バスの乗客はしかめっ面のアルゼンチン人から顔に皺を刻んだ、日に焼けたグアラニー族との褐色の混血に変わる。彼等は笑顔を絶やさない。言語も変わる。時々右隣のおじさんがグアラニ-語で筆者に話しかけてくる。その音感は韓国語ととてもよく似ているが、さっぱり分からないので適当にうなずいている。左隣の太ったおばさんに、
「全くちんぷんかんぷんだよ。ぼくは日本人なんだ」
というと、彼女は「そう」と言って笑っている。乗客たちは皆ビニ-ル袋にいれた細長いコッペパンをもっている。多分前からの知り合いというわけではなかろうが、互いにグアラニ-語で世間話をし良く笑う。共通の文化と共感に満ちている。いい意味で方言のきつい日本の地方を訪れたような錯覚に陥る。
まるでおとぎの国
首都のアスンシオンは田舎町の様相を呈していた。工場の煙突はどこにも見当らず、緑の木々と熱帯の美しい花々に囲まれていた。大統領官邸や国会議事堂にさえいかめしさは全くなかった。警護の兵士もチリの憲兵とは違い物々しさは感じられず、皆若い混血で何か緩い感じだった。大統領官邸の建物の回廊を歩いてうろうろしても何の注意もしてこない。これでは有事の際全く役に立たないのでは、とこちらが心配になってしまう。
街を歩けば中国人経営の中華料理屋、韓国人経営でハングル語の広告を出している商店が目立った。地方の農地には日本人の移民が多いのである。まるでアジアの一部のようである。
街歩きに疲れると、憲法記念広場の岸辺のベンチに座った。目の前のパラグアイ川が日射しを浴びてキラキラと宝石のように輝いている。以前、日本から商品を輸出したことがある。内陸国なので船はブエノスアイレスからパラナ川を経て、パラグアイ川にある港に着く。いや、商品は着かなかった。コンテナごと盗難にあった。輸入代理店の社長は港の税官吏でもあった。すなわち、自ら盗難し、実際はただで商品を手に入れたのである。損をしたのは、保険会社だけ。
また、ボリビア滞在中は、ラジオでチャコ戦争(ボリビアVSパラグアイのありもしない石油資源を巡る国境紛争 1932~38)でのストロエスネルの英雄的働きを称える、勇ましいパラグアイの短波放送のプロパガンダを始終聴いていたので、一体どんな国なのだろうかと心配していたが、来てみると、穏やかで自然の美しい桃源郷だった。
無論政治的言論の自由はなかった。共産党は被合法化されていた。娯楽は少なかった。それでも偶然再会した、世界50カ国を回ってきた友人が「ここなら住んでもいいな」と言うのである。
悲劇のパラグアイ史
グアラニー文化と混血
パラグアイは95%が混血でありスペイン語よりもグアラニー語が日常言語になっている。通貨名もグアラ二ーである。理由がある。パラグアイは内陸の奥まった場所にあり、金などの地下資源もない。スペイン人植民者の数も少なく、彼らは16世紀からグアラニーの習俗に従う必要があった。さらに、独立宣言後(1811年)、独裁者のフランシアは国家の安定のためにスペイン人とグアラニーとの集団結婚を奨励した(スペイン人同士の結婚は禁止)。こうして混血がすすんだ。
移民国の中南米はおうおうにして混血国家のほうが安定する。大地と外の世界の両方に左右の足を置くことができるからである。大地と歴史の正当なる継承者となり、土地は収奪するものではなく、何かを築くものとなる(対照が際立つ例は『アルゼンチンで繰り返される新自由主義とポピュリズム』参照)
だからこそ、パラグアイでは土地は公有化され、初等義務教育の制度が敷かれ、小学校が多数作られた。当時は周辺国とは違い、貧富の差のない、盗人のいない社会だった。
富国強兵殖産興業、そして国民の玉砕
1840年代には日本に先駆けて、三権分立の憲法を作り、欧州に留学生を送り、外国人技師を招聘し、製鉄所、武器工場、湾港などを建設し始め、軍隊も強化し、パラグアイ川沿岸に要塞も築き、南米最大の強国となる。資金は保護貿易の下、マテ茶などの輸出により賄われた。1861年にはアスンシオンに鉄道が開通している(日本は1872年が最初)。
ところがウルグアイの内政に絡む紛争から、アルゼンチン、ウルグアイ、ブラジルを相手にする三国同盟戦争が勃発(1864~70)。保護主義のパラグアイを良く思わないイギリスは同盟軍の後ろ盾となった。
多勢に無勢で国土は焦土化し、大統領のソラノ・ロペス以下、戦士の男たちは白虎隊のような子供たちも含め玉砕する。僅かな捕虜はサンパウロの奴隷市場で売り払われ、南米唯一の工業は壊滅し、公有地はブラジル人やアルゼンチン人の手に落ち、無償の義務教育も崩壊。国土の4分の1を割譲し、人口は戦前の半分以下の20万人前後、成人男性は3万人以下に減少し「女が木から落ちてくる」といわれる国家となった。(そのため、女が働き、男は子作りに励めばいいという文化が生まれた)。