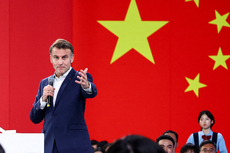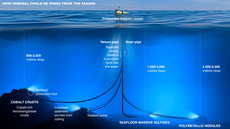環太平洋パートナーシップ協定(TPP)への参加問題で、政府の工程表によると農業強化策について今月21日には概要を策定すると明記している。TPP参加には、日本国内の農業改革が欠かせない。
しかし、減反政策や戸別所得補償制度があるため、増収によるコスト低減がタブー視される農業界。
だが、肥料や農機具が発達していなかった戦後間もない頃、1トンを超す多収穫を実現する農家がいた。
そして今、作物が健全に育つ土作り・田作りに取り組む農業経営者が現れ始めた。
タブー視される“増収”
我が国のコメ生産コストに関して、多くの人々は規模の制約でコストが下がらないと言う。規模拡大によって生産コストを下げる努力は当然行われねばならない。しかし、なぜ単位面積当たりの収穫量を増加させることによるコストダウンは問われないのであろうか。さらに、もし農業が農家にとっての仕事であるというのなら、我が国のほとんどの農家が他の先進国の農場と同じ程度の機械メンテナンス能力を持てないでいることのおかしさしさをなぜ問題にしないのだろうか。
“増収”という農業経営の本質的課題を農業関係者が語ろうとしないのは減反政策と矛盾するからである。また、小規模に趣味的な稲作をする農家を守るための農業政策がとられてきたからだ。経営力を持ち、技術能力も高いプロの稲作経営者も趣味的農家も同じ減反割合が押し付けられ、ほとんどバラマキ状態で交付される戸別所得補償制度。それらが増収を語らぬ農業界の精神風土を作りだしているのである。
1949年(昭和24年)から20年間にわたって「米作日本一」というコメの多収を競うコンクールがあった。日本の農家たちが最も意欲に燃えていた時代でもあった。
「米作日本一」の記録によれば、10アール当たり1トンを超すような多収穫を実現する農家も存在した。その一人である富山県魚津市の上楽菊(じょうらくきく)氏は1955年(昭和30年)に10アール当たり1014キロという超多収を実現している。55年の全国平均は396キロ。実に一般農家の2・5倍以上である。ちなみに、2009年産米の全国平均は522キロ。近年の平年作といわれる収量は530キロである。
化学肥料、農薬、農業機械などの進化と普及によって全国平均の収量は上がっているが、今の日本に1トンを超えるコメを取る農家はいない。
現在であれば、作付け前に1回与えるだけで作物の生育段階に合わせて必要成分が溶け出していくような便利な肥料や生育過程の様々な病虫害に対しても育苗段階に与えて効果を出せる農薬もある。暑い水田に這いつくばっての草取りや人力除草機を押してやっていた除草も1回の処理で長期間にわたって効果の出る除草剤を使う。除草剤を使わない栽培でも機械に乗っての除草作業も可能になっている。
そして、鍬(くわ)での耕うん作業も、今ではどんな小さな水田農家でも30馬力程度のトラクタを使うのは当たり前である。プロの稲作農家なら水田でも100馬力を超すトラクタを使う時代になっている。牛や馬の尻を追って鋤(すき)で耕していた時代には、馬で起こしてもせいぜい10センチ程度。今なら容易に25~30センチの深さに耕すことが可能でも、そうしたことを行う農家は限られる。
そんなことをしなくても、肥料でそれなりの収量が得られてしまうからだ。しかし、肥料で多収を目指すと食味や品質の低下は避けられない。化学肥料の無い時代に篤農たちが取り組んだのは、作物の根が健全に育つための深い、適正な排水のできる田を作ること、そして常に観察し、水管理で根の状態を健全に維持することだった。