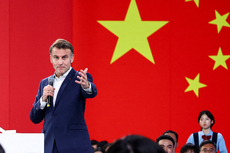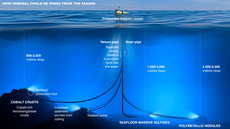2011年12月11日、南アフリカのダーバンで行われていたCOP17(第17回国連気候変動枠組み条約締約国会議)で、温暖化交渉の時代を画する合意がまとまった。京都議定書の延長が決まったと大きく報道されたが、実は合意の最大の意義はその逆で、京都議定書はその役割を終え、新しい時代に入ったことにある。
京都議定書が署名された1997年と現在では世界の経済地図が大きく変化している。2009年には中国が世界の温室効果ガス最大排出国となり、一国で世界の約4分の1を占めるに至った。今後はインドやブラジルなどの新興途上国の排出も増加の一方をたどることが確実視されている。
一方、これまで歴史的に排出の多くを占めてきた欧米などの先進国は、最近の経済不振もあって、排出のペースが落ちている。しかし京都議定書は、歴史的責任に着目して先進国だけに排出削減義務を課し、途上国には一切義務を課していなかった。そのうえ、そうした途上国への優遇を理由としてアメリカが脱退しているため、世界の約4分の1しかカバーしていない。京都議定書は、もはや実効的な温暖化対策とは言えない状況だった。
にもかかわらず、なぜ今回京都議定書が延長されたのか。それには欧州連合(EU)の政治的思惑が絡んでいる。これまで、EUは自ら京都議定書の生みの親であり、その後も温暖化交渉のリーダー役を自任していたが、ここ2年ほどはその存在感が失われていた。
背水の陣だったEU
2年前のCOP15では、米国のオバマ大統領が自ら交渉に積極的に乗り出した。会議の最終場面で、中国やインドなどの新興途上国に圧力をかけ、彼らの削減努力を外部から客観的に評価する仕組みを受け入れさせたが、EUはそのことを後で聞かされたのである。
昨年のCOP16では、EUは後手後手に回った前年の反省から、早い段階から京都議定書延長に前向きな姿勢を打ち出し、途上国の関心を向けさせようとした。最後は日本も延長に賛成するだろうと踏んだうえで、そうした動きに出たわけだ。しかし、閣僚会議初日に、日本が「京都議定書は既に有効な温暖化対策ではないとし、新たな枠組みを追求すべきだ」と主張。京都議定書第2約束期間の削減目標設定(いわゆる「延長」)を拒否して、新興途上国に対して一層の削減努力を促した。
この日本の態度が交渉の行方を決め、最後は新興途上国も一定の譲歩した結果、途上国の削減努力と先進国からの支援のバランスに配慮した合意に至った。ここでもまた、EUは外交的な存在感を示せなかったのだ。
その意味で、今年のCOP17は、EUにとって背水の陣だった。特にこの1年間、第2約束期間設定を匂わせ続け、さらに閣僚会議に入ってEUのヘデゴー環境大臣が早い段階でそのカードを正式に切ったことから、途上国の京都議定書延長の期待値は一挙に上がった。しかし、EUとしては、素手で帰国するわけにはいかない。ヘデゴー大臣は粘り、ほとんどの閣僚が帰国した11日日曜日の未明、自国の経済発展段階が未熟なことを理由に最後まで反対したインドの環境大臣との激しい協議の末、会議はようやく合意に至った。
同床異夢の合意 これからが大変
交渉では、EUは新たな枠組みが法的な拘束力があること(legally binding)にこだわり、他方、インドなどの新興途上国は先進国との「共通だが差異ある責任」の原則を崩すべきではなく、そのような拘束力がないものを目指していた。結果として「法的な力がある合意された結果」(an agreed outcome with legal force)という表現で妥協に至った。しかし、両陣営の考えを同床異夢的な表現で表したものでしかないから、今後始まる新たな枠組み交渉では、同じ論点を巡って火花が散らされるだろう。