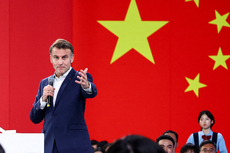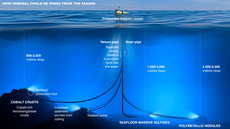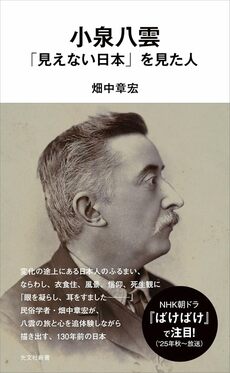大阪市西成区釜ヶ崎(現在の呼称は「あいりん」)。日雇い労働者たちが、簡易宿泊所に寝泊まりしたり野宿したりしながら、わずかな仕事の口を求めて集まる街。路上で寝ている人、車座になって朝から酒を飲んでいる人─という光景は、今も昔も変わらない。近年は行政やNPOが労働者たちの相談に乗るべく活動しているが、30年前、この街でそんなことをする人は数えるほどだった。
 入佐明美(いりさ・あけみ)
入佐明美(いりさ・あけみ) 1955年生まれ。看護専門学校卒業後、病院勤務を経て、80年より釜ヶ崎でケースワーカーを務める。著書に『地下足袋の詩』(東方出版)。 写真:田渕睦深
入佐明美は、1980年に看護師として勤めた病院を辞めて釜ヶ崎に入った。24歳の女性がケースワーカーの草分けとなり、800メートル四方の街にいる2万~3万人の労働者たちに、毎日声をかけて回った。入佐は今日も、自らの貯金と時折の講演謝礼と個人からの寄付を原資にして、事務所がわりとなる6畳・4畳半2間の文化住宅で、労働者の話に耳を傾けている。
驚くのは、アパート暮らしを望む労働者に、入佐が3万~6万円前後の私財を借用書なしで貸してきたことであり、その数が二百数十人に上りながら、最初の頃の4、5人を除いて全員がきちんと返済してきたことである。明日の仕事があるかもわからない人に、入佐はなぜ金を貸せるのか。労働者はなぜ遅滞なく返済するのか。そこから、人が人を信じるってどういうことなのかが、見えてくるように思う。
ケンカしたり酒飲んだりしたら
私が飛んできます
「最初は『私は看護師でケースワーカーです』と無我夢中で声をかけて回りましたが、ほとんど無視されるか怒られるか。結核の方に入院を勧めた時も『ほっといてくれ。どうせ仕事もないし、酒飲んで死んだほうが楽だ』って。それでも毎日、体調はどうか、なんで病院に行きたくないのかを聴いていたら、だんだん話してくれるようになって、1カ月半かかって『病院を世話してくれ』と言ってくれました。お見舞いに行って、その方がトイレに行っている時に隣のベッドの方が、『ねえちゃん、あの人は話を聴いてくれたことが一番ありがたかったって言ってたで』と話してくれました。これが私の根本となりました」
入佐は、中学校の道徳の時間に、ネパールの無医村で診療している医師を知り、自分も病気の人のために何かしたいと思った。9年後、看護師になった入佐は、日本に帰国したその医師に会いに行き、ネパール行きを直訴。その3カ月後、10人に1人が結核で、年に300人が路上で命を落としている釜ヶ崎でまず働いてはどうかと言われたことがきっかけになった。
「聴くとは、その人の存在そのものを受け止めることです。『病気なら入院だ』とこっちが主導権を持つのではなく、まず聴くことに徹したら、生い立ちを話してくれる方たちが出てきました。お父さんが戦争で亡くなった方が多かった。お母さんの再婚相手に虐待されたり、親戚中たらい回しにされたり、在日だといじめられたり。よくそんな中で生きてこられましたねという思いでいっぱいになって、その現実がすごいと、尊敬の気持ちが出てきたんです」