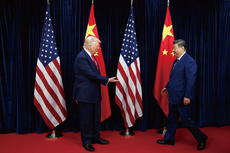バットを何本も持ったり、最新モデルのグラブを次々に買いそろえる家庭もあれば、野球はあくまで習い事の一つという家庭もある。さまざまな状況の家庭がそろうから、どちらが大勢を占めるかによって、チームの雰囲気も変わっていく。学年によって雰囲気が違う、というチームすらあり、自分の子が入ったチームの雰囲気が事前にわかりにくい面は否めない。
取材をした保護者の中には、「他の保護者のやる気がない」という不満もあったが、仮に「やる気がない」と批判される保護者に取材をすれば、全く逆の「熱心すぎる保護者がいて、息苦しい」という答えが返ってくるだろう。どちらの立場かで、保護者は「善」にも「悪」にも見えてしまう。
本企画の2回目「それでも野球を続けるために 動き出した新たなチーム」で紹介した。練馬や横浜のチームにように、既存のコミュニティーから飛び出して、自らが理想とするチームを作る人がいても、まだまだ一握り。大半は、近隣の既存チームに入るしかない。
少年野球は一度入ってしまうと、それぞれの保護者が役割を担っているので、やめることも難しい。ゆえに、すでに少年野球に携わっている保護者にとっては「当然」である「保護者の労力負担」「指導者の怒号、怒声」「金銭的な負担」が敬遠される要素となっているとみる。
令和時代の「効果的な一打」は
笹川スポーツ財団の宮本幸子政策ディレクターによる論文「子どものスポーツ活動をめぐる母親たちの社会関係資本-なぜ親たちは『周辺的役割』を担い続けるのか-」では、「子どもが地域クラブでスポーツ活動をし、母親の関与の度合いも高いグループ(参加群)」と「子どもが現在、スポーツ活動をしていないグループ(非参加群)」に対して、グループ・ディスカッションを実施した。
参加群は労力や時間に対する負担感や不安が高い点が共通したものの、自分たちが体を動かすようになったり、新たなコミュニティーの広がりというメリットを実感しているのに対し、非参加群は、学校を離れてまで、お母さん同士の関係が続くことに否定的な意見が多く、労力や時間の提供には「やるやらないも面倒だし、人間関係で『あの人はやってない』とかなる。……子どもがらみでそんなのは、親が疲れてしまう」「お茶当番、遠征に行くからと言って、車に子どもを乗せて乗り合いしたりとか。(中略)飲み会とか、そういうセッティングも保護者がやったり……それも嫌だなと思った」などと嫌悪感もあらわにしていた。
こうした保護者にとっては、もしも、自分の子どもが「野球をやってみたい」と口にしても、少年野球チームに入ることには高いハードルがあることが容易に想像がつく。
少年野球の競技人口は右肩下がりで減り、全日本軟式野球連盟が登録選手数を集計した2017年度は約20万5000人だったが、22年度は約17万人にまで減少。これは小学生に限らず、中学生でも同様である。さまざまな事情が複雑に入り組んでいる少年野球という特殊な世界において、この傾向に歯止めがかかる「効果的な一打」はいまだ見いだせていないのが実情である。(おわり。新たなテーマで不定期連載は続きます)