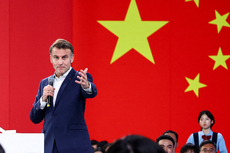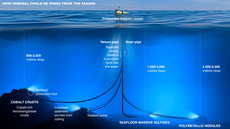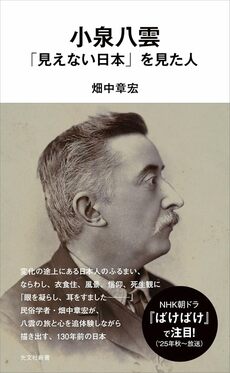NPO法人で育児支援などを手掛けるとともに、厚労省、内閣官房等のプロジェクト委員も務め、さらにイクメンでもある駒崎弘樹氏が、男の家庭への関わり方について論ずる。
 駒崎弘樹(こまざき・ひろき)
駒崎弘樹(こまざき・ひろき)認定NPO法人「フローレンス」代表理事・内閣府子ども子育て会議委員。1979年生まれ。99年慶應義塾大学総合政策学部入学。在学中にITベンチャーを起業。同大卒業後、共同経営者に経営権を譲渡しフローレンス設立。病児保育サービス、空き住戸を使った「おうち保育園」などを展開。1男1女の父で、誕生時にはそれぞれ2カ月の育児休暇を取得。(撮影・吉澤健太)
25年後、イクメンというライフスタイルはデフォルトになっている、というのが私の見立てだ。イクメン先進国・フィンランドを視察した際、政府関係者に聞いたところ、国民の意識が大きく変わったのはこの15年ほどのことだという。15年というのはいわば1世代。私たちが目の前の課題に取り組み続けていけば、子どもたちの世代にはそれが普通になっている、ということだ。
イクメンの定着により、働く女性が増えることは、日本経済へのプラス材料だ。先日、IMF(国際通貨基金)専務理事のクリスティーヌ・ラガルド氏が来日し、「日本は先進国の中で最も女性が働いていない。過去10年間で1人当たりGDPが0.9%しか上がっていないが、女性が先進国並みに働くだけで4%上昇する。なぜ今すぐ対策を講じないのか」と話した。全く同じ意見だ。
男性による家事・育児への積極的な参加は、実は有効な少子化対策でもある。第2子以降の出生率は、男性の家事・育児時間に強く相関するというデータが出ている。
家計にもたらすメリットも大きい。10年前、30代男性の平均年収は500万円台がボリュームゾーンだったが、今では300万円台にまで低下した。「夫が大黒柱となり、妻と子どもを養う」という旧来のモデルはもはや成立しない。夫が家事・育児に参加し、女性が働きに出ると、それぞれ300万円の収入でも合計600万円となって平均世帯年収(548万円)を上回る。終身雇用が崩壊した現状を踏まえれば、家計のリスクマネジメントにもなる。
イクメンという言葉は好意的な意味合いで世間に浸透した。次は実際の担い手を増やしていくことだが、そのためには上司層の協力が不可欠になる。だが、男性の育児休暇取得を不快に思う人の割合が約2割という調査結果もあり、育休取得率はわずか2%にとどまっている。