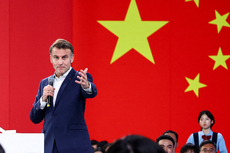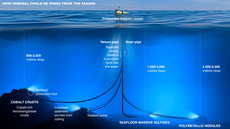ソニーとパナソニックが相次いでスマートスピーカーを発表しました。いずれも「オッケー、グーグル」と呼びかけて、クラウド上の音声アシスタントと自然言語で会話して、今日の天気を質問したり、ピザを注文したりすることができる製品です。もちろん、音楽をかけてもらうこともできます。すでにグーグルは、Google Homeという自社のスマートスピーカーを海外で販売しています。
スマートスピーカーはAIスピーカーとも呼ばれ、先行するアマゾンのEchoシリーズの累計の販売台数は、今年中に3000万を越えると予想されています。オンキョーも、アマゾンの音声アシスタント(Alexa)に対応したスピーカーを9月に米国で発売すると発表しました。
日本に導入される前に、スマートスピーカーは乱立状態になってしまっていますが、それは日本を代表するメーカーが手がけるべき製品とは思えません。その3つの理由は中国にあります。
その1. すぐにシャオミゼーションの餌食になる
グーグルのスマートスピーカーは、スマートフォンと同様の戦略上のものでしょう。Android OSをスマートフォン・メーカーに無償(他社の特許ライセンス料は別)で提供し、自社のプラットホームを拡大することによって、本業の広告ビジネスの増収を続けて来ました。アマゾンのEchoシリーズも、Alexaというプラットホームを拡大するための呼び水のようなもので、ハードウェアで大きな収益を上げようとは考えていないと思います。
音声アシスタントで、スマートフォンのアプリに相当するものは、アマゾンではスキル、グーグルではアクションと呼ばれています。音声アシスタントに対応するスマートスピーカーやその他のデバイスが増えることによって、スキルやアクションを開発するサードパーティにとってのプラットホームの魅力が拡大します。
2010年に設立された中国のシャオミ(Xiaomi)は、2014年には前年の3倍以上の6100万台のスマートフォンを販売して注目を集めました。その後、Eコマースに特化したマーケティング戦略とサプライチェーン・マネージメントで失敗したシャオミは、オッポ(Oppo)やビーボ(Vivo)といった同じ中国勢に抜き去られてしまいましたが、その「早く作って安く売る」というシャオミゼーションと呼ばれるビジネススタイルは、中国のメーカーに広く継承されています。
スマートスピーカーは、無線LANに繋がるマイコンにマイクとスピーカーを接続して、アマゾンやグーグルから提供されるソフトウェアを導入するだけで作ることができます。ハードウェアで差別化することは難しく、ソフトウェアやサービスはアマゾンやグーグルに握られているので、日本メーカーの製品は、あっという間にシャオミゼーションの餌食となってしまうでしょう。
さらに、ユーザーの行動や音声アシスタントとの会話はアマゾンやグーグルに吸い上げられるだけなので、スマートスピーカーのメーカーはデータを蓄積することができません。AIスピーカーといっても、メーカーのAI戦略にはなんら寄与しない製品なのです。