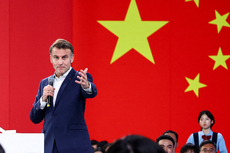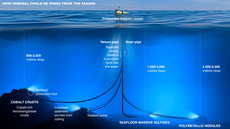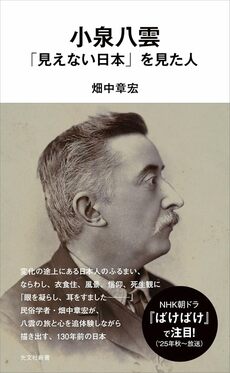ベトナムとの戦争の傷は、癒えていなかった、ということだろうか。この場合のベトナムとの戦争とは、米国のことではない。中国のことだ。通常は「中越戦争」と表記されているこの戦争は1979年に起きる。今年でちょうど40年を迎えた。

わずか1カ月に満たない短い戦争だったが、殺された双方の兵士の数は中越双方あわせて数万人を軽く超える凄惨なものだった。かつては兄弟国としてともに社会主義をアジアに広げていく夢を抱いた同士の近親憎悪がその根底にあった。中国側は、兄貴分としてベトナムを「懲罰」するという大義名分を掲げ、ベトナムは「侵略だ」と激しく譴責した。南シナ海をめぐる中越の対立の根っこにはこの中越戦争の後遺症による両者の不信と猜疑が横たわっている。
公開後1ヶ月で興行成績230億円という異例の大ヒットになった本作『芳華』に対して、中国で「これは傷痕映画」だと称する人もいた。中国には「傷痕文学」というジャンルがある。文化大革命によって受けた心の傷を出発点にして書かれた1970年代末期から1980年代にかけての文学のことだ。その映画版として、『芳華』は中越戦争の傷を負った人々の心を描いている、という解釈である。
中国映画で「戦争」がテーマといえば、日中戦争、そして国共内戦だ。この2つの戦争はいずれも「勝者」の物語で一貫している。だが、中越戦争で中国は勝者とは言い切れない。その意味でも貴重な価値のある本作は日本人も見ておくべき作品だと思う。
習近平夫人も所属していた「文工団」とは
映画の主題は、1970年代に軍の「文工団」に集った若者たちが、集団生活で培われた友情や対立をノスタルジーとともに蘇らせるもので、青春映画として、日本人にも理解しやすいテーマである。一方で、舞台となる文工団と中越戦争の二つに予備知識がないと、本作の深いところをすくい取れないかもしれない。
本作の主役たちが集う文工団とは「文芸工作団」のことだ。歌唱や舞踊、演劇を通して人民解放軍の将兵を鼓舞するために設けられたものだ。芸術や文化は政治に奉仕するべきだというプロレタリアート芸術観によって支えられており、映画のなかで文工団の練習場所にある「芸術は群衆に奉仕するものだ」というスローガンにその点がよく現れている。1970年代まで中国における文工団の規模は、日本軍がかつて持っていた慰問活動など及びもつかない組織的なものだった。全国各地から、文工団には歌や踊りが得意で、容姿も端麗な男女が集められた。

作中にもあるように、中越戦争の終了後、1980年代になって鄧小平が主導した改革開放政策が本格化すると、軍に対する慰問の必要性の減少から各地で相次いで解散されている。ただ、陸軍や空軍などの全国組織レベルでは現在も維持され、習近平国家主席の彭麗媛夫人もこの人民解放軍総政治部参加の歌舞団の出身である。
本作の映画監督の馮小剛は中国を代表する人気監督の一人だが、過去のトレンディドラマを思わせる軽妙なタッチの恋愛劇を得意とする作風と、本作の作り方は大きく異なっている。ただ、女性たちの軽妙な会話や早いテンポの展開は、重いテーマでありながら娯楽性を維持していくうえで十分な効果を生んでいる。

1958年生まれの馮小剛は、1978年、20歳で人民解放軍に入隊した。北京軍区の京劇団で美術部に所属して7年間の勤務を経て、1984年に人員削減の対象となって軍から転職を強いられ、映画の世界に入った。この作品の舞台もほぼ同じ時代であり、その意味で、本作は馮小剛の私小説的世界を演出したものだ。
だが、本作が中国で記録的なヒットとなった背景は、文工団へのノスタルジーだけではあり得ない。それは中越戦争の要素抜きには語れないだろう。