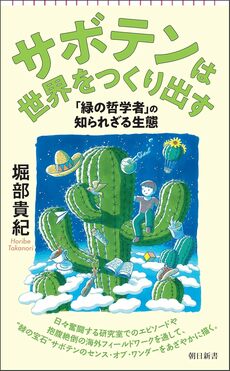SEALDsと「68年以降」の終焉
毛利 反原発運動や官邸前抗議行動も、新しい展開を見せ始めています。たとえば最近だと若い人たちのSEALDsの活動など新しいネットワークの作り方やデモの見せ方を示しているように思います。
僕はこれまでSEALDsについてはメディアからのコメント要請は全部断ってきました。契機となるようなタイミングでは何回か行ってはいるけど主体的に関わっているわけでもないし、メンバーを知っているわけでもない。そんな人間がもはや国民運動にまで発展している動きに余計なことを言うべきではないし、世間の彼らへの印象に誤解を与えかねないので、時期がくればきちんと調べた上で発言しようと思っています。でも、とにかくすばらしいと評価しています。
五十嵐 僕もそれほどフォローできていなかったんですが、8月30日(金)の「10万人デモ」は、見ておきたいという思いもあって行ってきました。本当によくやっている、と思います。
 SEALDsの奥田愛基さん
SEALDsの奥田愛基さん
毛利 法案の中身からメディア戦略まで、よく勉強していますよね。彼ら以上に深い議論があるのなら、それは専門家である研究者がやればいい。20代の学生があそこまでやっていることに驚かされます。
五十嵐 ほかの世代も彼らのムーブメントに加わっていますよね。いいことなんじゃないかな。
毛利 僕の本では『文化=政治 グローバリゼーション時代の空間叛乱』(月曜社、2003年) と、『ストリートの思想 転換期としての1990年代』(NHKブックス、2009年)の二冊がデモを扱っているのですが、どちらも渋谷や高円寺あたりのサブカルチャーから出てきた運動で、エッジが効いているのかズレているのかわからないような、社会から周縁化された異質な集団によるものでした。
今回は、政治色の必ずしも強くない大学に属している、ちょっと「意識高め」の層――これは否定的なニュアンスは一切ないです――大手企業やマスコミにでも就職していきそうな若者たちが、組織化して身を投じているところがまったく違います。だからこそ広がっているのだろうし、いろいろな層からの共感も得られているのでしょう。この点で、僕が分析対象としていた運動とは断絶があって、その前の反原連やレイシストカウンター運動はその転換期だったように思います。
五十嵐 そう思います。反原連は高円寺から始まったものでしたよね。
毛利 高円寺の人たちが後景化していくに従って、反レイシスト運動の「しばき隊」やC.R.A.Cなども出てきて、運動の主体が変容したんでしょうね。そしてSEALDsの登場で完全に入れ替わった。以前から運動をしてきた人たちには、ある種の寂しさがあるでしょうけど。
もうひとつ重要な点は、ニューレフト的なものでは完全になくなったことです。
五十嵐 そうですか。
毛利 ここでいうニューレフトと、日本語の「新左翼」と重なり合うところもあるのですが、日本の「新左翼」の場合は固有の歴史と党派性もあるので一応わけて議論したいと思います。グローバルな文脈におけるニューレフトは旧来のマルクス主義を超えようとして、環境問題、人種やフェミニズムといった階級以外の論点を取り入れようとしてきました。その流れにあったのがカルチュラル・スタディーズですよね。
五十嵐 ある意味で「差異のフロンティア」を探そうとしてきたということですね。
毛利 そのフロンティア探しは、反原発運動とSEALDsで完全に消滅したと思います。
五十嵐 そこも毛利さんにお聞きしたかったんです。安保法案をめぐる動きについては、僕もまったく発言してきませんでしたし、発言すべき立場にもありませんけど、そのあたりが社会学者にとっての発言しにくさに関係しているような気はします。
毛利 カルチュラル・スタディーズが発言しにくいのは、ニューレフトの系譜にいるからですよ。
五十嵐 ツイッターでSEALDsにまつわるセクシズムが議論になっていて、もちろん批判的に考えてゆくべきことではありましたが、当人たちの発言を見たり、伝え聞く限りでは、運動の中心になっている人たちは、そのあたりのことはわかっているんじゃないかって感じます。あえて清濁併せ呑む必要があるほどに、多様な人を巻き込む「国民運動」の段階に移行していた、それは確かだと思います。
毛利 嫌味っぽい言い方に聞こえるといやなんですが、いまの政治意識の高いと思われる多数派のミドルクラス層にこの短期間でしっかり訴えていくには、現実的にはああいう方法しかなかったのだと思います。