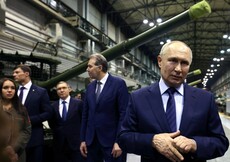あらゆる権威主義国家における祝祭とは、総じてこのような隠れた意図を宿しているものである。最も有名な事例としては、ナチス・ドイツが挙行したニュルンベルグの党大会や、天安門上の毛沢東が紅衛兵の大群を閲兵した文化大革命中の一大場面があるが、「金日成のパレード」も勿論例外ではない。日本時代の工業インフラが集中する北朝鮮は70年頃まで韓国よりも国力面で上回っていたといわれるが、党内分派が粛清され、金正日への権力継承がはっきりした頃から急速に斜陽の一途をたどり、ソウル五輪の開催にこぎつけた韓国に大きく水を空けられていた。それでも、当時はまだ90年代以後のような衣食住面での困難に直面していなかった。そこで、金日成を賛美する大規模な祝祭を行えば、辛うじて人々を幻惑させることで体制を維持できると考えたのであろう。総じて、体制や社会の危機を感じる権力であるほど、このような「幻惑の政治ショー」に訴えやすい。逆に、この手の総動員的な祝祭が少なければ少ないほど、その権力は安定している。
中国共産党の力を誇示した軍事パレード
では、建国60周年を迎えて天安門前での軍事パレードや大規模な祝祭を挙行した中華人民共和国が、果たして権力と祝祭をめぐるこのようなパラドックスから自由であったかと問えば、答えは勿論そうではない。今回の建国60周年祝典をめぐっては、外界では一人あたりのGDP水準と比べて著しく不釣り合いな最新鋭兵器に対する関心が高まったのは周知の通りである。しかし、それ以上に筆者が注目し、かつ嘆息させられたのは、祝祭の意図や方法において、21年前の北朝鮮と比べて何一つ変わり映えがせず、むしろ事前リークに対する厳しい取り締まり(例えば取材陣のPCが問答無用で破壊される等)を含めて、統制という側面でより「洗練」されていたことである。
天安門広場を埋め尽くした一大集団による絵文字が描き出したのは「党の声を聴け!」「党に忠誠を!」というスローガンであり、この国家とその軍隊が人民のためではなく、「人民を正しく指導しようとする」エリート集団・中国共産党のために存在していることを改めて明確に示しているかのようである。そして極めつけは、「56の民族が団結して単一の《中華民族》をつくっている」ことを表現するべく天安門広場の周囲に立てられた56本の柱「民族団結柱」であろうか。屹立する柱は、ヒンドゥー教的価値観においては男根を象徴しているように、しばしば「意志と威厳」を示すトーテムである。中国は、解決からほど遠い民族問題の現状に対し、真に実効性ある政策や対話で臨もうとするのではなく、必要とあらば「統一多民族国家の主体」たる「中華民族」なるものの「意志と威厳」を以ていつでも力でねじ伏せようということなのだろう。
60周年を迎えても政治体制の基本は変わらない
中華人民共和国の歴史は、早いもので毛沢東時代と改革開放時代がそれぞれ約半々となり、後者においてはそれまでとは比較にならないほど様々な事物が変化した。しかし、政治体制の基本は何一つ変わっておらず、むしろ89年の六四天安門事件やソ連崩壊をめぐって「西側の様々な干渉や経済・文化的浸透が中国の社会主義制度を平和的に転覆させようとしている」という認識=「和平演変」論が立てられ、それへの対抗としてより強烈なナショナリズム=「愛国主義」と富国強兵の動きが加速された結果、「愛国」と「富強」の担い手としての自己イメージを強めた共産党に対する異議申し立てはかえって難しくなった。しかも中国共産党は、激増する国富を背景として、ネットをはじめ社会の隅々にまで情報統制の網をかけるためのインフラ整備にも余念がない。中国との交流拡大が、自らのみならず中国の発展と開かれた未来にとっても有益だと信じて来た外界の人々が、中国の現状に強い違和感を抱くようになるのも当然であろう。中国脅威論の原因は決して中国の大国化そのものではなく、中国共産党の言行がまるで一致せず、「開放」と「和諧(調和)」の名の下で底知れない偏狭と抑圧がまかり通っていること自体にあることを中国は知るべきである。