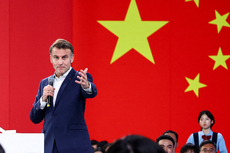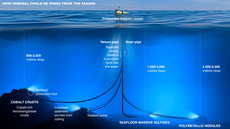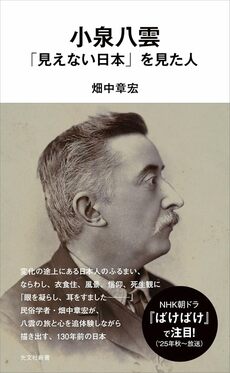子どもが熱を出すと、まるで四面楚歌の状況――。
「ちょっと子どもを見ていてもらえさえすれば、全然違うのに」と、都内に住む山野博美さん(仮名、39歳)は、途方に暮れる。
4歳の娘と1歳の息子を保育所に預けているが、悩みの種が尽きない。娘が熱を出した時、元気いっぱいな息子を保育所に預けてから娘を病院に連れていこうとすると、保育士から「お母さん、お休みですよね」と言って門前払いをくらった。「元気な息子を病院に連れて行って何時間も待つのでは、息子がかわいそう。なんとか、受診が終わるまで預かってもらえないか」と食い下がると、今度は「何かに感染して潜伏しているといけないので、元気でも登園しないでください」と冷たい。
一般的には、兄弟姉妹のなかで体調を崩した子がいた場合でも、多くの保育所で元気な子は預かってもらえる。感染症は発症する前日から感染力があるため元気な子の登園拒否には科学的根拠が乏しい。また、病気の子には親から看護される権利があり、元気な子には保育・教育を受ける権利がそれぞれあるため、本来は登園を拒否されるものではない。厚労省が定めているのは、特定の感染症に対する羅漢した本人の登園できない日数についてであって、元気な兄弟姉妹の登園の可否については国として通知などを出してはいない。ただ、博美さんの子どもが通う保育所では、親が休めば理由を問わず一切、子どもを預からない主義だった。(関連記事『締切直前、保育園選びのポイント解説』)
実家が遠く、両親も高齢で自由が効かないため助けは求められない。博美さんはやむなく、2人を連れて病院へ。周囲には咳こむ患者も多く、息子が感染するのではないかと気が気でない。やっとの思いで家に帰ると、熱でぐったりして母親から離れない娘と同じ部屋に、元気を持て余して外で遊びたがる息子がいる。しばらくはテレビを見せてしのいだが、そのうち「外に行きたい」と泣きわめき、「私が泣きたい」と思わず口にしてしまう。「こんな時、近所の人にちょっと見てもらうことができれば、どんなにらくか」と、博美さんは思えてやまないが、子どもを預けられる関係の“ご近所さん”はいない。
娘が治ったかと思うと、今度は息子が熱を出した。続けて10日も休むことになった。派遣社員の博美さんは、休んだ分は無給になる。こうしたことが年に2~3度続くと、決まって派遣契約は更新されず、事実上、派遣先からクビを切られてしまう。「せめて、保育園が元気な子だけでも預かってくれれば、きょうだいに風邪がうつらず、もっと休まなくて済んだのではないか」と落胆する。急な残業も同じだ。延長保育はその日の受付がなく、突発的な残業ができないばかりに「あてにならない」と派遣先から見られ、契約更新されない経験もある。そうした場合も「もし近所にお迎えをお願いして1時間でも見てくれる人がいれば」と痛感するのだった。地域の関係の希薄さと保育所の硬直的な運営が、博美さんの雇用を奪っていくようだ。
失われた10年から20年へ
これまで指摘したように、子育て世代の雇用のなかでも、特に女性の雇用は厳しい環境にある。それというのも、今、子育て真っ最中の年齢層のなかの多くに就職氷河期世代が含まれるからだ。まだ2000年前後の「失われた10年」と呼ばれるうちに社会に出た層は、そのまま不況のなかで「失われた20年」のなかにいた。
1980年代の大卒就職率は約8割を維持し続けていたが、91年のバブル崩壊を機に就職率は一気に低下して7割を下回り、97年の山一証券の破たんでまた就職が困難になっていく。2000年には統計上、初めて6割を下回る55.8%をつけ、2003年には最低の55.1%となった。2人に1人しか就職できなかった厳しい世代だ。その後、就職率は持ち返すものの、08年のリーマンショックでまた下降した。当然、非正規雇用は若年層にも爆発的に増えていき、そのまま中年層になっている。正社員でも少数精鋭で過酷な長時間労働を強いられる。そうした、超就職氷河期世代に学校を卒業してから30~40代に出産した世代が今、保育所を利用して働いていることになる。