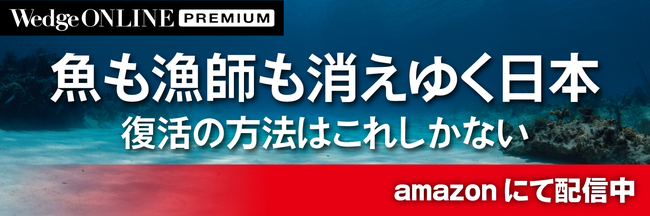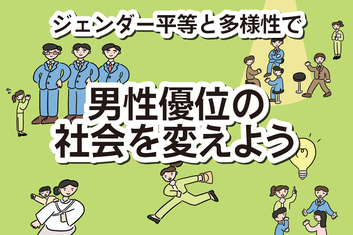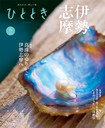乱獲の構造が変わらないため再び資源は激減へ
そして貴重なマサバ(太平洋系群)は、再び減少してしまいました。根本的な原因は資源管理の不備です。漁獲可能量(TAC)が実際の漁獲量より大きすぎるため、漁業者はサバの未成魚(3歳未満)を避けて漁獲するということはまずしません。
資源管理が進むノルウェーでは3歳未満の未成魚のサバを避けて漁獲します。漁船ごとに実際に漁獲できる漁獲量よりはるかに小さな漁獲枠が設定されているからです。
このため、単価が低い未成魚のサバを漁獲しない仕組みが出来上がっているのです。それにより漁獲されたサバの99%が食用となっています。
一方で日本の場合は0~1歳の食用に向かない未成魚のサバまで漁獲してしまうために、3~4割前後も非食用(養殖の餌)に向けられています。実にもったいないことです。
これから、世界人口の増加などで水産物の供給量は需要量を満たせなくなってきます。このためできるだけ食用に回す魚を増やさねばなりません。
未成魚が親魚に成長すれば、産卵する卵の量も増えて資源が好循環となるのです。しかし残念ながら今の日本はその逆となっています。
やはりいなかったサバの〝埋蔵金〟
サバ資源が多いという「誤った前提に対する正しい答え」は、獲り切れない漁獲枠の根拠となり、乱獲が進んでいます。漁業者は漁獲量の増加に期待しますし、水産加工業者は年々買付が難しくなっている輸入水産物の代替として期待していました。
しかしながら、それが裏目となり漁獲量は増えるどころか減少が続いて深刻な状況に陥っています。にもかかわらず、資源量が減少していることが明らかなのに、サバが深く潜っているとか、沖合にいるとかといったことが報道されていました。
筆者は、間違った情報が資源管理に与える悪影響を憂慮し、微力ながらWEB記事を通して「埋蔵金」のように期待されていたサバの資源は実際にはないことをデータを付けて発信してきました。今年(2024年)になって資源量が予想より35%低いと訂正されました。しかしながら、現実にはさらに悪くなっていることが懸念されます。
サバが獲れないのは①マイワシの資源量が多く、マサバが巻き網で届かない深さに潜っているから、②マイワシの資源が多くてマサバが近づけないから、といった報道がありました。
①については、日本の漁船と同じ漁場でサバの漁獲を行っているロシア漁船の漁獲量も大きく減少しています。ロシア漁船は日本の巻き網漁船と異なり、数百メートルの水深でも網を曳けるのです。
②マサバにとってマイワシは餌であり、なぜ餌に近づかないのでしょうか? データでは3歳以上マサバが多く、マイワシは小型が多く大半がフィッシュミール向けなので、サバにとってマイワシは避けるどころか餌になるのです。
マイワシに混じる大型のマサバの腹の中にはマイワシが入っています。また今よりはるかにマイワシが多かった80年代には、マサバもはるかにたくさん獲れていたなど、具体的にデータで矛盾を指摘しました。