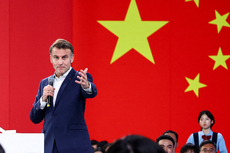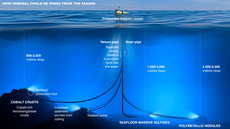『万葉集』といわれて思い出す歌は多い。次の数行も、ふとした時に口をついて出るもののひとつだ。
つぎねふ 山背道〔やましろぢ〕を 他夫〔ひとづま〕の 馬より行〔ゆ〕くに 己夫〔おのづま〕し 徒歩〔かち〕より行けば 見るごとに 音〔ね〕のみし泣かゆ そこ思ふに 心し痛し たらちねの 母が形見と 我が持てる まそみ鏡に 蜻蛉領布〔あきづひれ〕負〔お〕ひ並〔な〕め持ちて 馬買へ我が背
(巻13-3314)
巻13の長歌である。――正確にいえば、この中の、《他夫の 馬より行くに 己夫し 徒歩より行けば 見るごとに 音のみし泣かゆ》という部分を覚えている。
 photo:井上博道
photo:井上博道
人は、詩歌とさまざまな局面で出会うものである。わたしは、この一節を高校時代の古典文法の教科書で知った。見た瞬間に、
――ああ……。
と、思った。
文法の教科書――などといえば、一般的には無味乾燥の代名詞のようなものだ。しかし、読み方によって違って来る。わたしにとっては、日本古典中から引かれた、和歌や文章のアンソロジーでもあった。
おそらくこれは、助詞「より」の使用例として出て来たのだろう。手段・方法を表す用法で、《よそのご亭主は馬で行くのに、わたしの夫は歩いて行く》ということになる。そういう夫を見ると、どうしようもなく涙が溢れて来るのだ。
この思いは、《よその旦那は部長になったのに、うちのはヒラだ》といって不平不満をもらすようなところから、最も遠くにある。妻の心は、《徒歩より行》く夫のそれに寄り添っている。彼女は、彼を《甲斐性なし》などとは思わない。いわない――のではない。思わないのだ。《音のみし泣》くという、現代の詩で使われたら、大袈裟にしかならない言葉が、素直な真実の響きとなり、胸にじかに迫って来る。
学生時代には、女の友達がいて、一緒にお茶を飲んだり、映画や劇を観たり、本の感想を話せたりしたら、どんなに素晴らしいだろうと思ったものだ。だから、ここにある一体感が遠い、届かぬ花と見えたのだろう。
先生から、何の説明を受けたわけでもない。ただ参考として出ていた数行の言葉だ。それゆえ、ふと、ある女性の吐息を聴いたような気にもなった。

■「WEDGE Infinity」のメルマガを受け取る(=isMedia会員登録)
週に一度、「最新記事」や「編集部のおすすめ記事」等、旬な情報をお届けいたします。