人生も仕事も、この道を行きなさい、こうやって歩きなさいと、決めてもらうのが当たり前。だから、「最近の人は『こうしなさい』と言ってあげないと不安がる」との声は方々で聞こえるし、逆に言えば、定められたレールの上を踏み外さずに進むのが優等生ということだ。うまくいかなければ、悪いのは指示を与えた人か突発的な環境変化であり、自分自身が問われる部分は棚上げにされることが罷り通っている。
それじゃ人間は
機械と同じじゃないか
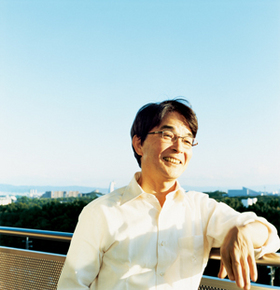 柳田敏雄(やなぎだ・としお)
柳田敏雄(やなぎだ・としお) 大阪大学生命機能研究科特任教授。1946年生まれ。71年大阪大学大学院修士課程を修了し、電子部品メーカーに就職した後、大学に戻る。88年大阪大学基礎工学部教授、96年同医学部教授などを経て現職。 写真:田渕睦深
指示や環境が悪いからなんて、人間ではなくロボットの話のようだ。生物物理学者の柳田敏雄も、そんな単線的な生き方は人間らしくないと笑う。その考え方には、生物の分子を観測してきた柳田ならではの説得力がある。筋肉の収縮を担う分子は、脳から一挙手一投足を指示されて動くのではなく、どこへ向かえばいいかを自分でふらふら動いて探すというのだ。ふらふらしながら自ら進む道を見いだすことにこそ生物の本質があるというのが柳田の持論だ。
柳田は電気工学を修めてエンジニアになったが、謎が多くて新しい概念をつくれる分野に挑みたいと大学に戻り、生物の研究室に入った。
「生物の中で一番なじみ深い器官が筋肉です。だから筋収縮の研究をやろうと思った矢先、ノーベル賞学者が新しいモデルを提唱して、謎は解けたとされてしまった。そのモデルでは、分子がコンピュータのように0か1かのデジタルで動くことで筋肉が収縮するという。それじゃ人間は機械と同じじゃないか、いくら偉い人が言っても、それはいかんと思いました」
筋肉の収縮は、アクチンとミオシンという2種類のタンパク質分子が担う。レール役のアクチン繊維の上をモーター役のミオシンが動くと力が発生し、筋収縮が起きる。では、どうやって動くのか。柳田が研究を始めた頃、ノーベル賞受賞者らが提唱した「首振り説」は、ATPというエネルギー物質1つにつき、四分音符のような形をしたミオシンが首を1回振り、ミオシンの頭が歯車のようにアクチン繊維の上を動くというものだった。生物は機械とはまったく違う仕組みで動いているとしか思えなかった柳田は、首振り説を否定しようと試みる。
「10ナノ(1億分の1メートル)の大きさのタンパク質分子を動く状態で見ることは原理的に不可能と言われていたので、それまでの人は、分子が何千兆個も含まれている細胞の動きを見て、分子の動きを推定していました。僕は、分子を直接見ないといかんと思っていましたから、レーザーを使って、何千兆個のいくつかをサンプリングして見ることに成功しました」
こう書くとあっさりしているが、ここまでに柳田は10年弱を費やしている。しかし、それでミオシンが0か1かの動きはしていないと否定しても、名もなき研究者の声は無視された。たまたま柳田の指導教授のもとを訪れ、実験装置や結果を見た米国人学者が支持を表明したことが契機となり、世界中が大騒ぎになった。

















