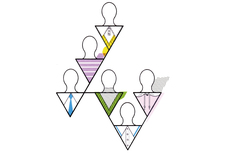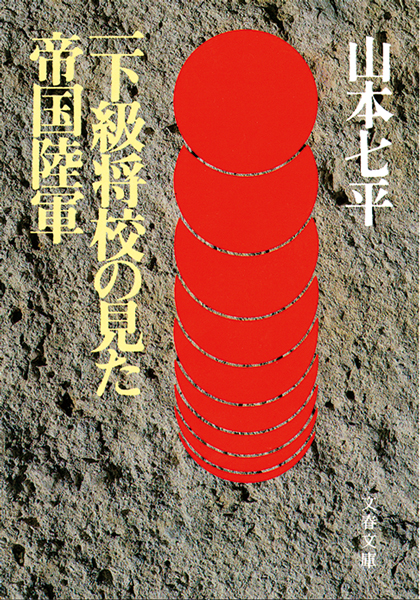
山本七平 文春文庫 726円(税込)
この書物は、過去の戦争のことを書いているはずなのに、読んでいると現代日本のことを書いているとしか思えなくなってくる恐ろしい書物である。言い換えると、太平洋戦争と組織・個人のあり方をめぐる書物は戦後多く書かれてきたが、その最高峰に位置するのが現代にもそのまま当てはまる分析を行ったこの作品なのである。
日本軍とはどのような組織であったのか。それは「員数主義」によって成り立っていた組織であったと山本は言う。
「『数さえ合えばそれでよい』が基本的態度であって、その内実は全く問わないという形式主義、それが員数主義の基本なのである。それは当然に『員数が合わなければ処罰』から『員数さえ合っていれば不問』へと進む。従って『員数を合わす』ためには何でもやる。
『紛失(なくなり)ました』という言葉は日本軍にはない。この言葉を口にした瞬間、『バカヤロー、員数をつけてこい』という言葉が、ビンタとともにはねかえってくる。紛失すれば『員数をつけてくる』すなわち盗んでくるのである。」
こういう組織が始めたのが太平洋戦争で、山本はフィリピン・ルソン島に砲兵隊本部の少尉として赴いた。
ルソン島カガヤン川のある場所で、左岸から「ゲリラヲ一掃スベシ」との命令を受けるが、「大体、左岸のゲリラを一掃せよなどという命令が、不可能命令である。米軍はすでに上陸し、彼らは十分すぎるほど十分に武器弾薬の補給を受け」「一方われわれはすでに補給ゼロ」「しかも相手は住民と区別がつかない。結局、討伐隊はこの不可能命令に対して員数報告を出す以外にない。すると『員数ではゲリラ、ゼロ』になる」
このように、不可能な命令を上から下された日本兵は仕方がないので兵員や兵器が欠けていても員数を合わせて報告する。この場合はあるものをないとする報告だったが、圧倒的に多かったのは実際にはないものをあるとする報告だった。この員数報告が積み上がり「『上は大本営より下は一兵卒に至るまで』を、徹底的にむしばんでいた」のが帝国陸軍であった。部下から上司へ「順調」な報告が上がる一方で、現実の戦況は確実に悪化し、敗戦へと向かっていったのである。
虚構の世界を「事実」とした末路
フィリピンのネグロス島は、日本軍が航空要塞を作っており米軍が手痛い被害をこうむるだろうと多数の日本兵たちが信じていた島だが、「どんな物かと思ったら」「毎日の爆撃で穴だらけになった飛行場群に焼け残りの飛行機が若干やぶかげに隠されているだけ」だった。「なぜこうなったのか。それは、自転する〝組織〟の上に乗った、『不可能命令とそれに対する員数報告』で構成される虚構の世界を『事実』としたからである。日本軍は米軍に敗れたのではない。米軍という現実の打撃にこの虚構を吹き飛ばされて降伏したのである。」
考えずに「自転する〝組織〟」というのはどういうものか。1943(昭和18)年8月に山本の部隊では初めて対米戦闘の教育が始まり出した。「われわれの受けている教育は、この『ア号教育』という言葉を聞かされるまで、 一貫して対ソビエト戦であり、想定される戦場は常に北満とシベリアの広野であっても、南方のジャングルではなかった」。ずっと「日本の陸軍にはアメリカと戦うつもりが全くなかった」からこうなったのである。「別にわれわれは、対ソ戦の要員ではなく、結局、それ以外のことは教える能力がないから、 今まで通りにそれを教えていたにすぎなかった」。
すなわち、陸軍という70年近い組織はすべてが規則ずくめで定型化して完結しており、それ自体の日常的必然というもので無目的な自転が行われていた。それは数さえ合っていれば、形式さえ整っていれば内実は問わない徹底した「員数主義・形式主義」の世界であり、不可能な命令とそれに対する員数報告で構成されるそうした虚構の世界は自滅していくしかなかったのである。そこからは、新しい発想、創造力、変転する情勢への主体的対処など出て来るわけがなかった。