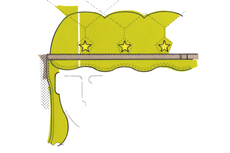天平建築の雰囲気をもつ作品展示館内で談笑する赤水さんと筆者
天平建築の雰囲気をもつ作品展示館内で談笑する赤水さんと筆者
黄のパジェロで高台の作品展示館へ先導される。館内の大窓は日本海の絶景である。
「こんな日は1年で3、4日しかありません。シベリア風がまもなく吹きます」
鏡のような海に黒い礁(いくり)が点々と散らばり、水平線へあこがれを奏でる。まだ見ぬ美の沖を目指す赤水さんのようだ。
「水は低いところへ向かって流れます。この辺なら山の水はみんな日本海へ流れこむ。同じように、窯のなかの炎は煙突を目指す。その炎の流れがこの黒い窯変です」
無名異焼は従来、酸化炎で焼く赤い焼き物だった。黒は不良品とみなされた。それを赤水さんは、窯の中で思わぬ変化を遂げた「窯変」と、プラス思考で捉え直すことにした。意識的に還元炎を浴びせた黒は、赤い色面と緊張関係を生み出し、見るものを悠久の時にいざなう。逆転の発想は、無名異焼を工芸品から精神性を湛えた芸術へ一挙に高めた。
沈黙の花、抑制の美
 色土のパーツを細密に組み合わせて花を表現した「無名異練上花紋盒」
色土のパーツを細密に組み合わせて花を表現した「無名異練上花紋盒」
「新しいフィールドにつねに自分を乗っけていかなければならない。ある日、組み土で花を作ろうと。平面でなく3次元の遠近ができたらいいな。花の向こうにある花。さらに向こうを」
無名異練上花紋盒(むみょういねりあげかもんごう)に、息を呑む。誰も一見蒔絵を疑うだろう。しかし、表面に描いた花の絵ではない。色土を組み合わせた練上手による、裏まで通った土の花である。
「太巻き寿司を作るようですよ」
それは、謙遜。花びらの一ひら一ひらまで、赤白黒の土のパーツを細密に組み合わせる気の遠くなるような作業だ。
練上の先達に、同じ人間国宝の松井康成がいる。斬新華麗な作風で、晩年の絢爛な花紋には目を奪われる。いっぽう、赤水さんの花紋は原初的(プリミティブ)だ。花々はうす墨色の闇につつまれ、渦巻くように地の底から湧き上がる。紅を帯びて。トキ色にかがやいて。清冽な蕊(しべ)。なかに大きな牡丹のような花がある。風車(かざぐるま)なのか。銀河なのか。大輪の花びらのふちというふちが闇へそよぐ。風にあえぐ。手に触れれば絹よりもすべらかだ。墨色の余白を湛えた沈黙の花は、語り飽きることがない。
 乾燥途中の練上花紋角壺。花紋を組むとき自然にかかる指の力で土がゆらぎ、それがつぼみをほどいて咲きゆらぐ花の繊細な表情につながるという
乾燥途中の練上花紋角壺。花紋を組むとき自然にかかる指の力で土がゆらぎ、それがつぼみをほどいて咲きゆらぐ花の繊細な表情につながるという
「凝(じっ)とこらえた末に咲く花。抑制された花ですね。世阿弥の花に重なります」
肉迫、という言葉が浮かんだ。薄紙を剥ぐような切ないまでのそれが。
「椿ですか。牡丹ですか」
「花、いう花です」
解けるどころか謎は深まるばかり。それでいいのだ。