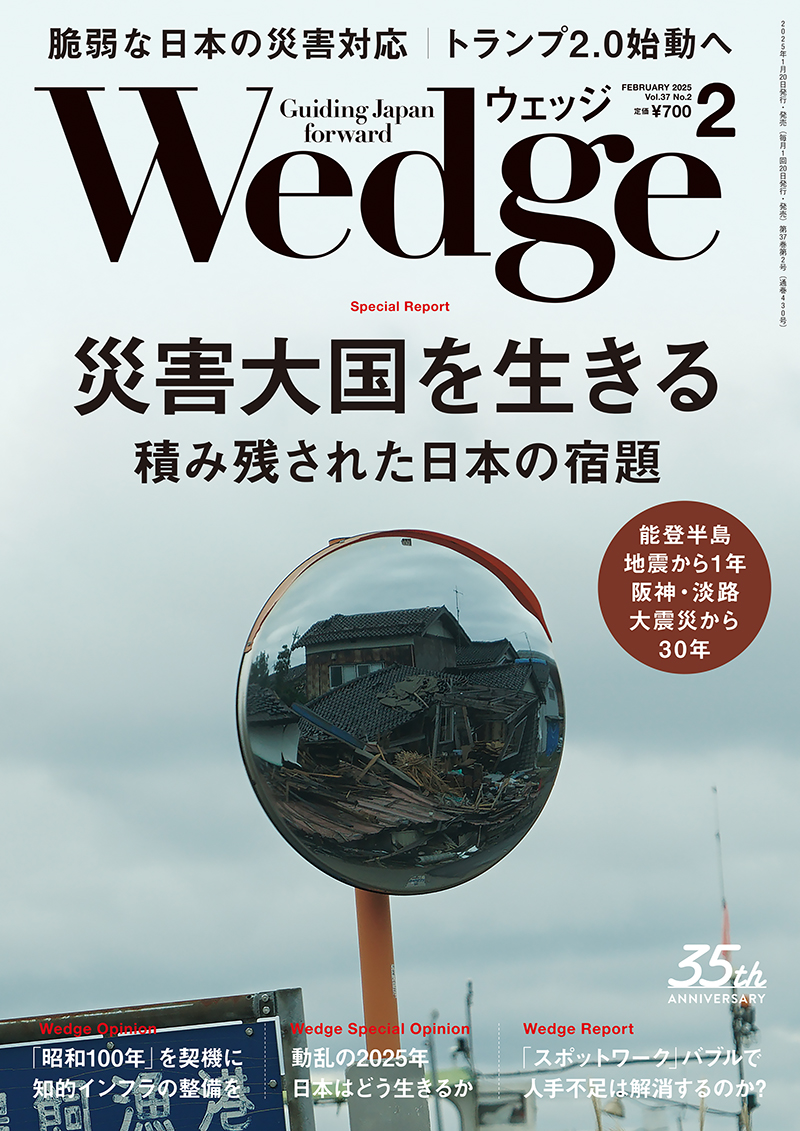「作り手は真の使い手であれ」
「かまどさん」の取説の受け売りですが、火を消すまでの13分間、「かまどさん」は徐々に蓄熱をしています。だから「はじめちょろちょろ」で、次第に温度が上がって「中ぱっぱ」が起こります。そして、火を切った後も、100度近い蓄熱が30分程度続くので、薪の竈にできる熾(残り火)と同じく、「赤子泣いても蓋とるな」という「蒸らし」が行われているのです。
「かまどさん」には、おいしさを閉じ込める「中蓋」も付いていますが、陶器だけに壊れるリスクもあります。
「それで使うのをやめたというお客様もおられましたので、パーツ販売も開始しました。ただ、窯で焼く陶器は、置かれた場所によって収縮率が微妙に異なるため、お客様に蓋や鍋の直径を聞く必要があります」
手間がかかるので、反対する意見もあったそうですが、大産地のように分業が進んでおらず、自社で一貫生産しているからこそできるサービスということで実施したところ、大好評になりました。こうした顧客第一の姿勢の背景には「作り手は真の使い手であれ」というこだわりがあるのです。
また「食卓は遊びの広場だ」という精神のもと、「いぶしぎん」という土鍋燻製器も開発されています。康弘さんのご息女で広報・Web担当の早紋さんによれば「ベーコン鍋を食卓で囲めば、大盛り上がりします」とのことで、早速試してみたいと思います。長谷園さんではゴールデンウイークに「窯出し市」というイベントを行っており、約3万人の来場があります。
また、登り窯や、国の登録有形文化財の建物もあって年間では5万人もの観光客が訪れるそうです。決して便利な場所にあるわけではありませんが、行くだけの価値はある場所だと思います。500円で陶器付きコーヒーが飲めるので、お土産に最適です。