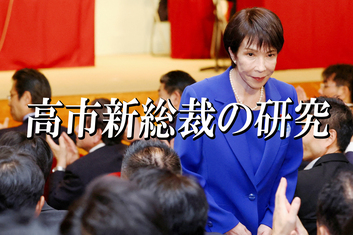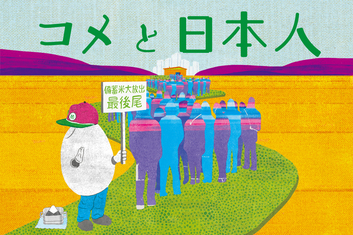富士フイルムによれば、メディベクターはCRO(治験実務の調整会社)ではなくコンサルティング会社で、アメリカでの「開発パートナー」。当初、アメリカでの治験は、現地CROを使って富士フイルムが直接実施していたが、フェーズ2の途中からメディベクターに委託し、そこからの治験主体はメディベクターになっているのだという。
”アビガンのライセンスは両社にある”
「開発パートナー」とは何か。なぜアメリカでの直接治験をやめることにしたのか――事情の呑み込めない筆者に対し富士フイルムは、「ライセンスアウト(特許・知財の譲渡)したわけではない」と折に触れて強調したが、ホワイトハウスのリリースを読んでいくと、12月2日付に「アビガンのライセンスは両社にある」とあった。
これもまた驚くほど知られていない事実であるが、アビガンはすでに富士フイルム単独の薬でなくなっている可能性があるのだ。
これに対し富士フイルムは、「アビガンの海外における開発および製造販売に関する全ての権利は富士フイルムが保有しており、メディベクター社に対してはアビガンの米国での臨床開発をライセンス(委託)しているだけである」と説明している。【2014/12/26追記】
米国陸軍感染症医学研究所(USAMRID)の 最高研究責任者を務めるシナ・ババリ博士は去る14年12月2日、東京大学で実施した講演会で、「アウトブレイクは必ずまた起きる。また、エボラを含むフィロウイルスは生物兵器として使えるポテンシャルを有する」と結論づけ、「イスラム国のような集団がすでに入手している可能性も否定できない」とした。
同氏によれば、エボラやマールブルグといったフィロウイルス類は旧ソ連においては生物兵器として重点課題に掲げられ、1980年代にはそのために6万人近い人が雇用されたという。
冷戦時代より、アメリカにとって感染症対策は国防の問題であった(Wedge12月号記事「エボラは国防 ウイルスを奪い合う列強」を参照)。アメリカでは、エボラやアビガンに関する予算は、国内外の民間企業に対するものはもとより、CDCに対しても保健省からではなく国防総省から拠出されている。
外国の薬であるアビガンに目をつけ、国際援助の名の下に軍隊を現地に送りながら、治験のためのアフリカと交渉をいち早く始めたアメリカの外交力には舌を巻く。
それにしても、アメリカがこれほどの資金を投入し、アビガンにこだわる理由はいったい何なのだろうか――詳細は12月20日発売のウェッジ1月号「数奇なる エボラ薬『アビガン』の素性」をご一読のほど。
![]()
![]()
![]()
▲「WEDGE Infinity」の新着記事などをお届けしています。