――変化の早い時代に、まじめにお金をかけて研究などしていられないという理屈なのでしょうか
自分でコツコツと特許を作ってゆくのが昔ながらの王道です。しかしそうではなくて、グーグルにしろ、アップルにしろ、自分でやっている時間はないので、買ってくればいいという発想です。特許を買ってくるというのは新しいやり方で、新興国企業も今はそれを当然のようにやりますね。
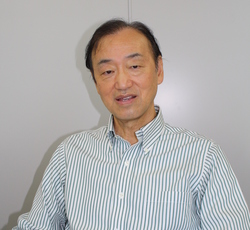 久慈直登(くじ・なおと)
久慈直登(くじ・なおと) 1952年、岩手県生まれ。学習院大大学院修了、ホンダ入社。ホンダの初代知的財産部長を2001年から11年まで務める。2012年より日本知的財産協会専務理事、2014年より日本知財学会(IPAJ)副会長。
――買ってくるというのはどういう意味ですか
特許の市場みたいなものができていて、それを何千件かまとめてお金を出して買い、自社のものにしてしまう。自分で開発したのと同じように使えるということです。
――値段は自社開発するより安いのですか。時 間を買うという意味もあるのですか
そういうことです。アメリカでは1件の特許は5000万円ぐらいです。5000万円の価値があるとみて売買される。そういうのは、10年前ぐらいまではあまりなかったことです。研究開発は自分でやるものだという意識でした。それが今は、IT産業などでどんどん新興企業がでてくると、必要な技術が十分ないから買ってこようという動きが加速している。そういう時代に、日本企業が単に自分で研究開発しようと言っていたら、出遅れますね。
――確かに買った方が効率的だし、むしろ安かったりするかもしれません。そうした発想は日本企業にはなかったのでしょうか
少なくとも2004年~5年ごろまでは、日本企業の力はものすごく強かったですから、強い時期はやり方を改めない。それが、その後十年ぐらいの間でどんどん変わってきている。今がその変化の時期にあたっているのですけれど、そうした時期に状況はどういう風に変化しているのか。やはりここでも情報をどう認識するかが重要です。それをわからずに昔のままやっていたら、負けパターンです。変化が激しいのはやはりこの十年です。心ある企業はどんどん変化しているというのも事実としてあります。世界で戦っている企業はだいたいそのように変化してきていますが、そうでない国内中心だとか、地方の中小企業になると、まだまだ古典的なやり方を続けているところも多いです。
――大企業ではどんな会社が先進的な取り組みをしているのですか
世界で戦っている電機 IT デジカメ、自動車などもそうですし、巻末につけた表の世界シェアの上位の産業は必死になってやっています。いうなれば世界のリーダー企業ですから。
――マンパワーや資金のある企業ならいいですが、地方の中小企業などには確かに難しい面もあるかもしれません。そうした企業をサポートするようなソリューションビジネスなどはないのでしょうか
そうした企業も少しずつ出始めています。もっと動きを加速させないといけないといけません。私の本などもそれを加速させるための一つのサポートになればいいと思っています。
――本書でとりあげられているケースは、まさにタイトルのように「喧嘩」です。パテントトロールに狙われてしまう企業の傾向などはあるのですか
あります。狙われる企業は徹底して狙われる。一言でいうと、弱くてポリシーがしっかりしておらず、脅せばすぐお金を払うような企業です。残念ながら上場企業でもそういうところがある。例えば、日本企業の判断の仕方として、訴えられて弁護士費用が2億円かかるという時に、相手が5000万で和解しませんかといわれてふらふらする企業がある。その時に無理しても裁判で勝っておかないと、お金を払ったという情報がトロール側に全部流れて、別のトロールからも狙われる。そういう仕組みをしらないといけない。相手は交渉相手の顔や性格も熟知して分析していて、どの担当役員を狙って脅しをかければカネを払うということまでわかられてしまっているケースもあります。
――実際日本の大企業でもあるのですか
ありますね。対処法としては、断固として対応し、相手が仕掛けているとおもったら、仮に自分の普段の性格が温厚であっても演技しないといけない。怒ったり、逆に脅すような感じになることも時に必要でしょう。それが世界との戦いということです。穏やかに話してすむような場面ばかりではないのは確かです。
――そういうケースはこれからも増えますか
増えると思います。知財だけがそういう場面で使える武器というかツールです。新興国企業は今後、知財で攻めてくると思います。特に中国などは、知財という武器で戦いを突きつけてくると思うんですね。それは当然、中国が世界に出て行くときに、欧州やアメリカの企業に対しても同じように突きつけているはずで、欧米企業で力のあるところは逆に中国の企業をやっつけにゆくでしょう。

















