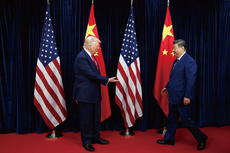日本ではとかく共産党権力による言論統制が話題だが、「商業化」という影響力がもはやそれ以上に彼らの意識の中に根付いていることを感じさせられた。
このことは中国のメディアが共産党権力から大衆という権力の下に移行し始めたことを意味しているのかもしれない。
「個人の責任として原発取材を行いたい」
この中国側代表が使った「商業化」という言葉を「市場」に置き変えれば、日本のジャーナリズムが置かれている環境と何も変わらないことに気づかされた。
討論の中では、また両国のメディアが似通った特徴になりつつあると思われるやり取りも少なくなかった。例えば、「3・11」東日本大震災をテーマに話し合ったときだ。中国側の代表の一人は、未曾有の災害を前に一人の部下が、「会社に一筆入れ、個人の責任として原発取材を行いたい」と申し出たエピソードを披露したのだ。
日本側からは、「そこまですれば良いっていう話じゃないのでは?」といったつぶやきが漏れていたが、違和感を覚えたのは程度の点で「やり過ぎ」と感じた部分であって、決して根本の動機に対するものではなかったはずだ。
実際、雑誌には政府の避難指示を無視したレポートがいくつも掲載されている。それは市場を巡る競争のなかで差別化を意識して行き着いた行動といえるだろう。少なくとも親方「五星紅旗」で身分が保障され、突出した行動をしても決して評価されない時代の発想ではない。
その意味では記者のインセンティブにも明らかな“近似”が意識された。
日中関係好転に結び付くとは限らない
ただ、問題は日中のメディアの体質が接近しているからといって、それが日中関係の好転と結び付くとは限らないと思われることだ。というのも、日中のジャーナリストのインセンティブの近似は、互いの論調が政治判断ではなく社会の“空気”により重きが置かれることが懸念されるからだ。これは先に引用した中国側代表の表現を借りれば、記者が“ショー”を前面に出した記事を書かさざるを得ない状況を意味している。
会議では日中メディアの危機管理として「記者の理性」や「客観的な報道」、「事実の追求」といった意見が日本側から出されたが、熱狂する大衆が正面から向き合う時代を迎えようとするなかで、こんな耳ざわりの良いだけの言葉がどこまで通用するのだろうか。
対する中国側代表のほとんどは、荒ぶる民意の台頭(とくにネット上において)に対し、強い警戒感を示していたことが印象に残った。
◆本連載について
めまぐるしい変貌を遂げる中国。日々さまざまなニュースが飛び込んできますが、そのニュースをどう捉え、どう見ておくべきかを、新進気鋭のジャーナリスト や研究者がリアルタイムで提示します。政治・経済・軍事・社会問題・文化などあらゆる視点から、リレー形式で展開する中国時評です。
◆執筆者
富坂聰氏、石平氏、有本香氏(以上3名はジャーナリスト)
城山英巳氏(時事通信中国総局記者)、平野聡氏(東京大学准教授)
※8月より、新たに以下の4名の執筆者に加わっていただきました。
森保裕氏(共同通信論説委員兼編集委員)、岡本隆司氏(京都府立大学准教授)
三宅康之氏(関西学院大学教授)、阿古智子氏(早稲田大学准教授)
◆更新 : 毎週月曜、水曜
■「WEDGE Infinity」のメルマガを受け取る(=isMedia会員登録)
週に一度、「最新記事」や「編集部のおすすめ記事」等、旬な情報をお届けいたします。