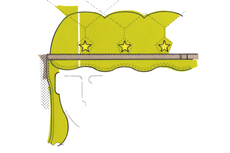選挙戦が繰り広げられている第51回衆議院議員解散総選挙で、与党、野党のほとんどが消費税の減税を主張している。一方で、2006年の79兆6860億円から26年度政府予算案で122兆3092億円へと拡大を続ける政府予算の規模を恒常的に反転させようとする提案は聞かれなかった。
それどころか、今後も政府の役割は大きくならざるを得ないので、安定財源をどう確保するのか、未来に責任ある議論が必要との声が、政治にも、メディアにも、国民にも溢れている。経済政策においては、与野党ともに一致して「左派」であり、「大きな政府」とする公約が与野党ともに一致するかのように掲げられ、国民も支持する様子が見て取れる。
日本人はなぜ、政治家も国民も大きな政府を好むのか? その傾向を理解するうえで、戦時体制と統制経済の経験は決定的な意味を持つ。明治期に始まった国家主導型近代化は、戦争という非常事態を契機に、国家の役割をさらに拡大させた。
特に昭和期における戦時体制は、国家が経済・社会のあらゆる領域を統制する仕組みを確立し、国民生活を国家が直接管理するという構造を生み出した。この経験は、戦後の日本人の「国家依存」意識を強化し、大きな政府への支持を定着させる要因となった。
明治期に端を発する国家主導の理論的支柱
日本人が「大きな政府」を自明のものとして受け入れ、危機の際に行政の保護を強く求める心理の深層には、昭和前期の戦時統制経済の経験が横たわっている。しかし、この時期の体制変革は、決して突発的な転換ではない。その実態は、明治以来の「富国強兵」と「殖産興業」を掲げて進められてきた、国家主導による近代化政策の最終的な総仕上げであったと言える。
明治政府が近代国家の範を求めたのは、自由放任主義(レッセフェール)の英米ではなく、ローレンツ・フォン・シュタインやアドルフ・ワグナーらに代表されるドイツ財政学の発祥の地ドイツであった。国家が社会の安定を設計し、産業を保護・育成すべきであるとする「国家有機体説」を受け継ぐドイツ財政学は、後発国日本の理論的支柱となり、官僚による市場への介入を「文明国の責務」とする学問的土壌を形成した。
そして、このドイツ系財政学・行政学を中核とする学問体系は、1880年代以降、ドイツ留学から帰国した金井延や戸水寛人らによる帝国大学等における教育を通して長期にわたり再生産され、官僚や学者をはじめとするエリート層に「国家による積極的介入こそ近代国家の本流である」という価値観を深く根づかせた。こうした学問的伝統は現代にまで及び、いわゆる有識者の側にも構造的に大きな政府を支持しやすい思考枠組みが形成され、国家の役割を縮減する方向への議論が主流化しにくい風土が確立したのである。