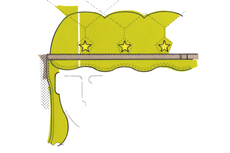公立学校の教員採用試験(2024年度実施)の倍率が2.9倍(前年度は3.2倍)となり、過去最低を更新したというニュースが関係者に衝撃を与えている。教員志望者の減少傾向は、もはや統計上の問題ではなく、「来るところまで来た」という現場の悲鳴として受け止められている。
崩れた「3倍神話」
筆者は、県教育委員会で勤務していた際、教員採用試験(正確には選考試験)に関わった経験がある。面接では、一部の自治体において、評価の多様性を確保するため、民間企業の人事担当者など、教職以外が面接官として参加することがある。
その中で、一流企業の人事担当者が「落ちる受験者全員が欲しい」という言葉を試験終了後に思わず漏らしていた。日本の教員志望者の水準の高さを、あらためて印象づける一言であった。
しかし、今その水準が危うい。
教員採用の現場では、「3倍神話」と呼ばれる考え方が長く共有されてきた。すなわち、教育の質を確保するためには、最終的に採用したい人数の少なくとも3倍程度の倍率が必要だ、という認識である。
倍率がそれを下回れば、教育の質が揺らぐ――少なくとも採用現場では、そう受け止められてきた。教員の資質低下が指摘されて久しい中で、「2.9倍」という数字は、そうした危機感を客観的に可視化したものと言える。