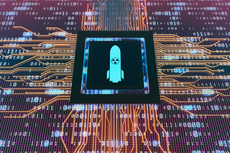教育無償化について、自民・公明両党と日本維新の会が党首会談で合意した。この合意では、高校無償化について2026年度から収入要件を撤廃し、私立加算額を全国平均授業料の45万7000円に引き上げるとされている。先行措置として25年度から所得制限を撤廃し、全世帯を対象に支援金11万8800円を支給するという。(「自民・公明・維新が高校無償化等で合意 来年度予算成立へ」)

(Milatas/gettyimages)
これにより公立高校は所得制限無く授業料が実質的な無償化に、私立高校についても保護者の金銭的負担は大きく下がることになる。公立と私立の学費差が大幅に縮まることで、生徒は家庭の経済事情によらず高校を選択しやすくなるという。(もっともこれは授業料の話である。私立学校では施設費やその他費用も多額であり学費が全て無償になるというわけではない。)
一方で受験競争の若年化や公立離れが懸念されている。実際に京都府や兵庫県では少子化の影響もあって私立中学の受験者数が昨年に比べ減少しているが、すでに高校無償化に取り組んできた大阪府では逆に7.1%も増えた。同様に昨年から私立高校に通う生徒に約48万円あまりを支給していた東京都では、都立高校の平均倍率が1.3倍から1.20倍に急減したという。(高校の授業料“無償化”も…専門家「教育負担は減らない可能性」【サンデーモーニング】)
実は高校無償化の動きは10年に民主党政権下で始まっている。その後自民党政権になってから紆余曲折があったものの、今回は拡充が図られた形だ。背景としては昨年の選挙結果による与野党の駆け引きがあることは間違いないがここでは政治的な問題は他に譲り、高校無償化が公立と私立の学校教育にもたらす影響について見てみたい。