1930年代の新聞記事を一つ紹介したいと思う。日本で留学生生活をした朝鮮人留学生の短い回顧だ。私がこの記事を紹介したいと思ったのは、先日韓国で起きたある事件がきっかけだ。
2020年10月12日、韓国の有名小説家が「日本に留学を行ってきたらみんな親日派になってしまう。民族反逆者になる」と発言し、物議を醸した。発言したのは趙廷来氏(77)で、販売累計1500万部を記録した韓国を代表するベストセラー作家の一人だ。
この発言の背景には、去年日韓両国でベストセラーになった『反日種族主義』(参考記事「2カ月で10万部『反日種族主義』、韓国人著者たちの受難」)の著者李栄薫元ソウル大学教授との因縁がある。李教授は以前から著書や論文で趙氏の小説『アリラン』を日本に対する間違った認識を定着させた代表的例として挙げてきた。趙氏の小説には日本の警察が朝鮮人を銃で脅し、処刑したりする場面が登場するのだが、それは虚構であり、趙氏の小説は「狂気に満ちた憎悪の歴史小説」であると批判したのだ。
自分の代表作を学者に公開批判された趙氏が不愉快になるのは当然だ。さらに『反日種族主義』が日韓両国で注目を浴びたことで、自分の名前と作品が再び世間で話題になった。その「感情」が今回の「日本留学生=親日派」発言として表れたと思われる。
日本へ留学生した人の特徴を一言でまとめるのは不可能だ。時代によって、環境によって、人によってその個性も反応も違うからだ。朝鮮が合併された日本統治時代にもいろんなタイプの朝鮮人留学生が存在した。アルバイトを余儀なくされた苦学生、富裕層の子息で遊びに明け暮れた学生、抗日運動をした学生、親日派になった学生など多種多様な学生たちが同時に存在した。それを思えば小説家趙氏の「みんな親日派になる」という言葉が乱暴な物言いであることは間違いない。
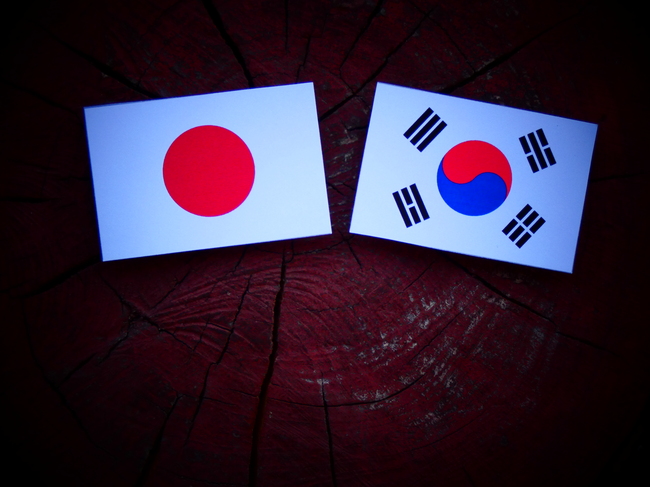
では、日本統治時代を生きた朝鮮の内地留学生たちは日本でどのような生活をしたのだろうか。その一面を覗くことができる一つの記事を紹介したいと思う。1935年東亜日報の記事である(原文は韓国語)。
「懐かしさ」と「不快な体験」が共存した東京生活
そして、その中で見られる「本音」
東京生活追憶
極熊
東京を発ってからもう何年も経ってしまったように感じるのに実際に数えてみれば1年余りしか経っていないことを思えば月日が流れるのはとてもゆっくりのようで、私が新聞社に入ったことを考えれば昨日のことのようなのに、あと2カ月ほどで1年になるのだから月日が経つのはとても速いようにも思えてくる。いずれにせよ、日々が過ぎ、月が流れていくにつれ益々東京について思うことが増えていく。今でも私の体が東京にいるかのようだ。
私が東京を忘れることなどできるはずもなく、さらに忘れることができないのが人情だ。私が20歳になった年に東京に行きそこで成長し、そこで修養し、そこで未熟ながらも仕事をしてきたのだから、思い出さないわけがないということだろう。
時間的に見たとしても18年という短くない年月、つまり、本国にいた時間と同じ時間なのだが、本国で過ごした10歳以前の出来事は覚えておらず、覚えていたとしていたとしてもあやふやなものだから数に入れる必要がないとすれば、本国にいたのは10年位だったのと同じことで、東京では20年間過ごしたといっていい。20年間東京の空気を吸い、東京の土の臭いをかぎ、変化に満ちた東京の空をしょっちゅう見上げ、湿気の多い東京の気候に慣れてしまった私に、どうしたら東京を思い出さずに居られるだろうか。私が頻繁に訪れていた九段坂、神保町、駿河臺、小川町、小石川、白山坂はありありと目に焼き付いているし、私が住んでいた麹町中六番町、日本女子大学の奥にある雑司谷、大塚坂下町、滝野川西原浦田町の通りがいつでも浮かんでくる。
暑苦しく蒸した夏の日、一日中疲れきるまで歩き回り、ひとっ風呂浴びて熱い番茶を飲みながら涼しい風に当たるとか、陰湿に寒い冬の日、冷え切った足と体をコタツの中に突っ込んで暖をとるとかいう東京だけで味わうことのできる風情が、今になってこんなにも懐かしく思い出されるのだ。私が少しばかり苦労して修養していたのも東京で、少しばかり事業経験を積んだのも東京だ。恋愛経験をしたのも東京、3、4人の娘を授かり、育てることになったのも東京で、私と東京には深い因縁があり、故郷は生まれた場所というだけで、思い入れのある場所は東京だと言わざるを得ない。
今でも繰り返し思い起こし、忘れることが出来ないのは私のことを心配してくれ、助けてくれていたR君やP君で、また3、4年の間私の学費を出してくれたのはK会だ。S氏やC氏からは私が東京にいた間、最初から最後まで厚意に預かり続け、多くの援助をいただいた。私は私のこの肉体が朽ちるまでこの恩を忘れないことだろう。
しかし東京は良い印象だけを与えてくれた場所ではない。つまり、いくつもの不快な出来事もあった。貸しますと言ってもらった借家も、朝鮮人だと名刺を差し出すと態度が変わり、翌日に返事を聞きに行くとなんだかんだと言い訳され、拒絶された。もちろん東京にいる我が国の国民が家賃をきちんと払わないことや、家を不潔に使用するということが大きな原因であったのだから、過失はむしろこちら側にあり、向こう側にだけ問題があるということもできないわけで、このような経験をするたびに激しい苛立ちを覚えたことだけは事実だ。
家を借りて住むようになっても、近所の人たちから「朝鮮人」だと 大人子供がコソコソ話され、後ろ指を指されることは決して気分が良いことではなかったし、ある席では打ち解けて話していたのに原籍が朝鮮だという話が出たとたんに、不自然な表情を浮かべられ、それ以降はお互いに気まずくなってしまうようなことがしばしばあったが、これもやはり愉快なことではなかった。
いつでも朝鮮人だと悪口を言われないように細々と神経を使い人の目ばかりを気にして過ごし、新聞にでも朝鮮人についての良い記事が出た日には道を歩くのも堂々としたもので、少しばかりの慰めになったが、そうでなかった日には自ら心を閉ざすしかなく、居心地が悪く、まるで町内の人たちが私を白い目で見ているようで、悪口を言われているように感じていた。私一人が失敗したことが朝鮮人全体を悪く言われる原因になり、私一人が良いことをすれば朝鮮人全体が評価されるのだと考え、どこに行っても朝鮮人の代表の資格で参加したのだと考え、過ごしていたのだ。一言で言うなれば薄氷の上を歩くかのように戦々恐々としながら、注意深く過ごしていたのが東京生活だった。
東亜日報 1935.6.23

















