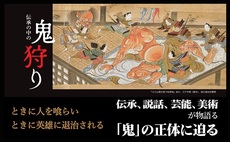「日本を もっと、考える」をテーマに、Wedge ONLINEでは世の中の“いま”を深掘りする情報をお届けしています。
今回は2024年5月11日~5月24日に多くの方に読まれた記事・TOP5を発表します。
第5位からの発表です!
<目次>
第5位:〈高付加価値の丸太生産に専念できない国有林の苦悩〉木材販売からみた国有林事業の不思議
第4位:【退職代行は“正義”なのか?】若者の働き方に飛び交う「やさしさ」、本当に自分のためとなる選択とは
第3位:〈戦後の日本人画家が歩んだ数奇な運命〉故郷を失った藤田嗣治と国吉康雄、そのアメリカでの〈対決〉
第2位:《宇野昌磨の引退》フィギュアは「自分を出しやすい場」、人前で話せないゲーム好きの少年が世界をけん引するまで
第1位:年々上昇を続ける生涯未婚率…法的拘束に縛られない「事実婚」を選ぶワケ
第5位:〈高付加価値の丸太生産に専念できない国有林の苦悩〉木材販売からみた国有林事業の不思議
樹木の販売方法には2つ、森林を生えたままの立木(たちき)で売る立木(りゅうぼく)販売と、森林を伐採して山元で丸太に加工してから麓に運搬して、貯木場(営林署が管理する公営の施設)や木材市場(もくざいいちば)、製材所に持ち込んで販売する製品販売がある。
筆者は昭和の終わりごろ、熊本県球磨郡に所在する多良木(たらぎ)営林署長をやっていた。人吉・球磨地方は多良木の名のとおり良質のヒノキの産地で、林業・林産業が盛んだった。木材市場はこの地方に複数あって、それぞれ月に3回丸太の競り売り(市売り)があったから、週に2回以上はどこかで市が開かれていたことになる。
木材市場は民間経営のため、主に民有林から伐採・搬出された丸太を競(せ)りにかけて販売している。ただ、営林署の丸太は70~80年生の高齢材で買い手に人気があったため、各木材市場からは客寄せの目玉商品として出品希望が高かった。筆者は、販売業務に興味があったので、営林署材が出品される市にはできるだけ参加した――。
【続きはこちら】
〈高付加価値の丸太生産に専念できない国有林の苦悩〉木材販売からみた国有林事業の不思議
第4位:【退職代行は“正義”なのか?】若者の働き方に飛び交う「やさしさ」、本当に自分のためとなる選択とは
新年度も1カ月以上が過ぎ、5月の大型連休も終わった。古くから“5月病”という言葉が知られているように、この時期には新しい仕事環境へのストレスから憂鬱になったり、場合によってはそのまま退職してしまうケースも少なくない。そうした中、急速に注目を集めつつあるのが「退職代行サービス」だ。
「4月だけで1397名(うち新卒208名)の退職を確定させました。
大企業が一社潰れる数値です。
5月以降の予約も101件となり、GW明けの退職者は更に加速します。
賛否両論あるかとは思いますが、日本の退職は悪という風潮が少しでも和らぎ、退職代行の存在で労働者の立場を少しでも向上させることができればと思います」
4月30日、退職代行サービス業者の一つ「モームリ」はX(旧Twitter)でこのように語った。退職者の割合は新卒が比較的高いものの、幅広い世代から利用されている実態も見えてくる――。
【続きはこちら】
【退職代行は“正義”なのか?】若者の働き方に飛び交う「やさしさ」、本当に自分のためとなる選択とは
第3位:〈戦後の日本人画家が歩んだ数奇な運命〉故郷を失った藤田嗣治と国吉康雄、そのアメリカでの〈対決〉
後に文化勲章も受賞した洋画家・野見山暁治はその年の秋に出征のため東京美術学校、いまの東京芸術大学美術学部を繰り上げ卒業しているから、『アッツ島玉砕』と作者の藤田嗣治の姿を見たのは卒業直前の1943(昭和18)年9月に上野の東京都美術館で開かれた〈国民総力決戦美術展〉の一場面であろう。
〈学校で絵を描いていたら誰かが面白いぞ、と大声をあげながら教室に入ってきた。今なァ、美術館に行って、お賽銭箱に十銭投げるとフジタツグジがお辞儀をするぞ。本当だった。隣の美術館でやっている戦争美術展にさっそく行ってみたら、アッツ島玉砕の大画面のわきに筆者の藤田嗣治が直立不動でかしこまっていた。当世規定の国民服で、水筒と防毒マスクを左右の肩から交互させて背負っている。脚には革の長靴をはいて、ともかく見事ないでたちだ。もちろん頭は五分刈りだったが、これもまた似合っている〉(野見山暁治『四百字のデッサン』河出文庫)
『アッツ島玉砕』は日本の敗色が強まる第二次世界大戦後期、厳寒の北太平洋の孤島で上陸する米軍との過酷な戦いの末、ほぼ全滅する日本軍の断末魔を大画面に描いた作品である。倒れた累々たる兵士たちを踏み越えて、軍刀を手にして突き進む隊長の山崎保代を中央に配した褐色の画面は重苦しいが、惨い戦争の現実をたしかに伝えている――。
【続きはこちら】
〈戦後の日本人画家が歩んだ数奇な運命〉故郷を失った藤田嗣治と国吉康雄、そのアメリカでの〈対決〉
第2位:《宇野昌磨の引退》フィギュアは「自分を出しやすい場」、人前で話せないゲーム好きの少年が世界をけん引するまで
フィギュアスケート男子で五輪に2大会連続出場した元世界王者の宇野昌磨さんが、21年間の競技生活に終止符を打った。身長157センチと小さな体でコツコツと積み上げた努力で五輪では個人で銀と銅の2つのメダル、団体でも銀を獲得し、世界選手権では2連覇を成し遂げた。
近年のフィギュア男子を人気、実力の両面でけん引してきた26歳は競技から離れても、フィギュアスケートからは退くわけではない。プロスケーターへと転向し、「自分の生き方に合っている」と話す自由なフィールドで表現に磨きをかけて新境地を切り開く。
東京都内で5月14日に開催された記者会見には、大勢の報道陣が集まっただけでなく、所属してきたトヨタ自動車のオウンドメディア「トヨタイムズスポーツ」で午後2時から一般視聴者へ向けてライブ配信も行われた――。
【続きはこちら】
《宇野昌磨の引退》フィギュアは「自分を出しやすい場」、人前で話せないゲーム好きの少年が世界をけん引するまで
第1位:年々上昇を続ける生涯未婚率…法的拘束に縛られない「事実婚」を選ぶワケ
『負け犬の遠吠え』が出版されたのが2003年です。この本は、当時、ベストセラーとなり、「負け犬」は、2004年度流行語大賞でトップテン入りも果たしました(ちなみに大賞は、「チョー気持ちいい」でした)。
ところで、著者の酒井順子さんが書いていた「負け犬」の定義をご存じですか? 書籍の冒頭の部分を抜粋します。
さて、それから20年近くが経ちました。今の日本はどのようになっているでしょうか。総務省統計局の国勢調査を見ると、「生涯未婚率(50歳時点で一度も結婚したことがない人の割合)」は、年々上昇を続けており、1980年頃まで5%を下回っていたものが、2020年調査では、男性が25.7%、女性が16.4%に達したという結果になっています――。
【続きはこちら】
年々上昇を続ける生涯未婚率…法的拘束に縛られない「事実婚」を選ぶワケ