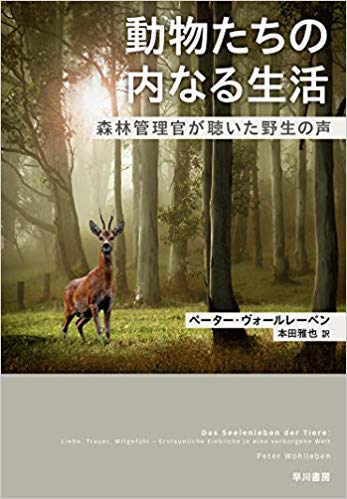人間に勝るとも劣らぬ感情豊かな内面
ペーターが本書でふれる動物たちは、実に多種多様だ。アリやハチ、チョウやガといった昆虫、苔の中に暮らすクマムシ、森に住むシカ、イノシシ、ノロジカなどの狩猟動物、カラスやカケス、シジュウカラなどの鳥類、ドイツでは身近なリスやハリネズミ、そして家畜としてのウマ、ヤギ、ブタ。ペットとしてのウサギ、イヌ。手話をするゴリラなども登場する。
ヒトと生活圏を接するそんな動物たちの行動をつぶさに観察し、野生の声に耳を澄まし、そこから垣間見える彼らの「内なる生活」を探る。明らかになるのは、私たち人間に勝るとも劣らぬ感情豊かな内面である。
動物を単純に擬人化するのではなく、学問的厳密さを保ちつつ、動物たちとの日々の交流で得た直感を控えめに語る態度が好ましい。
「学問的な知見を、小説のように読める」本を目指している、と著者自ら語ったように、読者はわくわくしながら動物たちの行動を追い、ページを繰るうちに動物のことをより深く知るようになる。
たとえば、ワタリガラスが公平不公平に対する強い感受性を持っている、という話。共同作業と道具の使用に関するこんな実験が紹介される。
<二羽のカラスが同時にかつ慎重に糸のそれぞれの端を引っ張れば、糸が抜けることなく二羽はごちそうを届くところまで引き寄せることができる。そのことを賢い動物であるカラスは即座に理解するが、パートナー同士が仲の良い場合には、この実験はとりわけうまく運ぶ。だがこの綱引き作業をした別のペアでは、首尾良くチーズを引き寄せたあと、一羽がふた切れとも食べてしまうことがあった。働いてもなにも得られなかったカラスはそのことを覚えていて、それ以降そのいやしい仲間とは、ともに作業しようとしなかった。エゴイストは鳥の世界でも好かれない、ということなのだった。>
そういえば、森のカラスも、いつもの支柱に穀物のおすそ分けをもらいに来る前に、地面をつついてナラの実を隠していた。穴を複数開けて、ペーターを欺く工夫までして。
「与えられた食べものをもっとも効率よく食べるための、完璧なタイム・マネージメント。そしてそれを実現するために、カラスは未来にかかわる思考を展開していたにちがいないのだ」と、ペーターは気づく。
「これから動物を観察するときはもっと細かい点まで見よう。さらに言えば、自分がほんとうはなにを見たのか、もっと綿密に考えよう。それに皆さんだってどうだろう、こんな体験に出くわして、あとになってその真の意味に気づく、なんてことがきっとあったのではないだろうか」
家畜の悲惨な飼育環境や遊びの狩猟に対する憂慮
本書を読めば、ある種は賢いとか、かわいいとか、ヒトにとって善か悪かといった分類がいかに不遜でばかげたことであるかに気づかされる。なにしろ動物たちは、私たちが思ってもいないようなやりかたでこの世界を知覚しているのだから。
ブタやニワトリなど食肉にされる家畜の悲惨な飼育環境や遊びの狩猟に対しても、ペーターは遠慮がちに憂慮を表明する。私もまったく同感である。
<動物にも感情があると認めることへの拒否反応にたびたび接していると、人間がその特別な地位を失ってしまうことへの不安感がそこには見え隠れしているなと、ふと感じることがある。(中略)……私が望むのは、今の世界をともに生きるものたちと付き合うなかで、それが動物であろうと植物であろうと、彼らへの敬意が少しでも戻ってくれればいいな、ということである。そのことが利用の断念に直結するわけではない。しかし快適さとか、生物由来の製品の消費量などをあるていど制限することにはつながるだろう。それが楽しげなウマやヤギ、ニワトリ、ブタの姿として報われるなら、(中略)――そのときは、私たちの中枢神経系のなかでホルモンが放出され、抗いようのない感情が体じゅうに広がるだろう。ああ、幸せ!>
![]()
![]()
![]()
▲「WEDGE Infinity」の新着記事などをお届けしています。