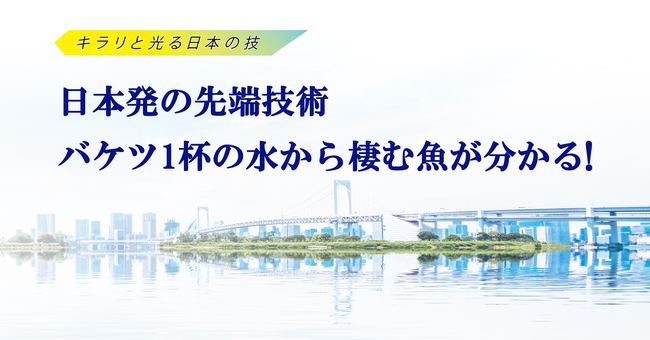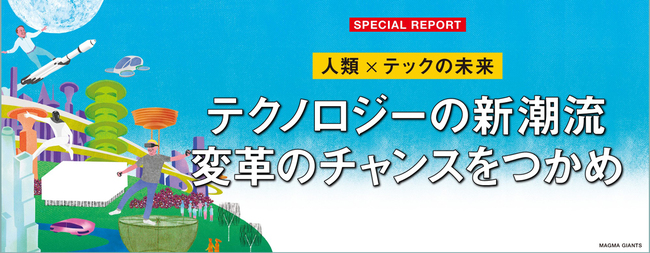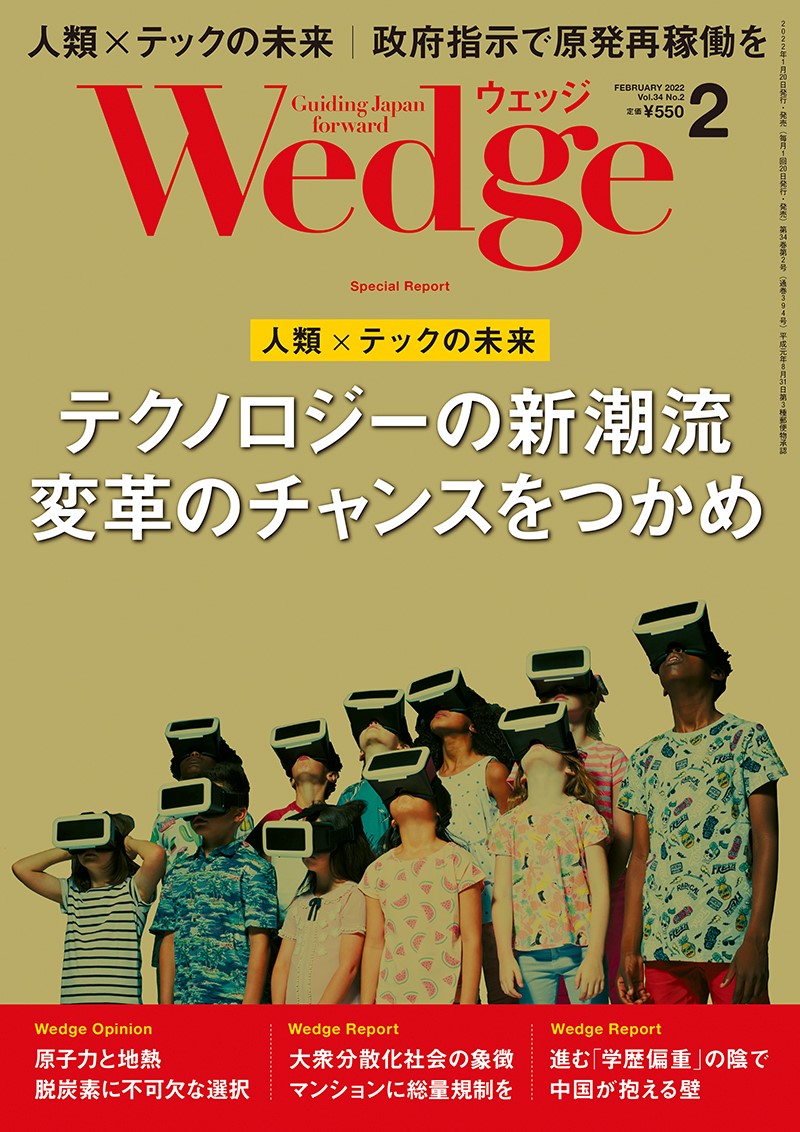生物学で扱うものとしては最もサイズの大きな「環境」と、最小レベルの「DNA」がくっついた何とも奇妙な言葉である「環境DNA」。これを使った技術が生き物調査のありようを大きく変えようとしている。
実際には「環境中のDNA」という意味で、土壌も対象にできるが主には「水中を漂う生物由来物質からのDNA」を指す。魚の場合、表面の粘膜やフンなどに含まれていたその魚のDNAが水中へと出て行き環境DNAとなる。
本稿で紹介したいのは、1㍑の水に含まれる環境DNAを解析することで、その水域に棲む魚のリストが得られるという技術だ。ほんの7年ほど前に日本で開発されたばかりだ。
海や川などでそこに棲む魚を調べようとすると、従来は、網などで実際に捕まえるか、研究者が水中に潜るか、水中カメラなどを使うほかになかった。人手も費用もかかり、気軽にはできない。さらにそうやって得た魚や画像からそれが何という魚種であるかを調べなければならない。「同定」と呼ばれるこの作業は専門家でないと難しい。魚は種類が多くて、図鑑を使うことさえ素人には簡単ではないのだ。
環境DNAを使う調査法では、調べたい海や川の水をバケツですくい、その水をフィルターで濾しとる。フィルターに残っているものが試料となる。現場で行うのはここまでで、あとは研究室での作業となる。試料に含まれるDNAを抽出して、解析しやすいようにPCR法でそのコピー数を増やし、DNAの塩基配列を読んでいく。読んだ配列を公開データベースの登録データと突き合わせ、種の同定を行う。
この調査方法の良い点は、……
◇◆◇ この続きを読む(有料) ◇◆◇
◇◆◇ 特集の購入はこちら(有料) ◇◆