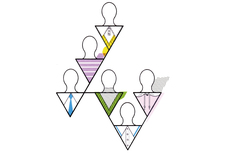そう遠くない昔、この国の勤労者は大半が「会社命」だった。あの企業との一体感、エンゲージメント(従業員の仕事に対する熱意)はどこへ行ったのか。2022年のギャラップ社の調査によれば、日本の従業員のエンゲージメントの度合いはわずか5%。米国の35%はもちろん、中国の18%にも遠く及ばない。日本の5%は、世界平均21%の4分の1以下なのである。
さらにパーソル総合研究所がアジア太平洋州14カ国・地域を対象にした調査では、「現在の勤務先で働き続けたい」と考える日本人の割合は52%で14カ国中最下位。インド、ベトナム、中国のそれは80%以上となっている。
「選択と集中」によって
「捨てる」「諦め」てきた日本企業
背景には、日本の企業が終身雇用制を放棄し、「選択と集中」と称して、多くの事業を「諦め」、切って捨てた事実がある。捨てる経営がいい経営、と讃える風潮さえあった。なるほど事業を「捨てる」のは企業には効率的な「選択」なのだろう。が、現場の勤労者にとっては「すべて」の喪失なのである。
「日本的経営」の強さは現場力だった。強い現場は「考える現場」である。日々、知恵を絞り、カイゼンし、また考える。現場にとって、事業は日々の実践であり、生きがいであり、人生そのものだ。その事業が目先の利益のために、あっさり捨てられた。現場が白け切るのは、当然すぎるほど当然だろう。
日本の半導体産業は1986年、世界トップに立った。そこから先、坂道を転げ落ちるように、縮小と衰退の道をたどった。当時の半導体のリーダーはNEC、日立、東芝、松下電器という総合電機である。重電(発電プラント)や家電というドル箱が安定的に稼いでくれるのに対し、半導体はシリコン・サイクルに翻弄される。数百億、数千億円の投資を余儀なくされ、巨額の赤字リスクに晒される。経営者たちは現在の安定を選択し、将来の可能性を「諦め」てしまった。
87年、まさに日本が半導体トップに立ったその翌年、半導体の大投資を決断する李健煕がサムスン会長に就任し、モリス・チャンが台湾積体電路製造(TSMC)を創設する。半導体が決定的な新時代に入ろうとするその時、日本の「諦め」が始まった。韓国や台湾に走った日本の半導体技術者は「裏切り者」との罵声を浴びた。順番が逆だろう。経営側がまず、事業を諦め、現場の技術者たちを裏切ったのである。