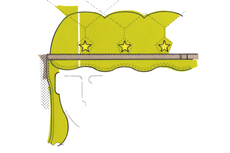第一次世界大戦(1914~18年)は軍事史上に一転機を画した大事件だったが、同時に政治的、社会的意味においてもメルクマールとなる出来事であった。
第一次世界大戦は単純な帝国主義的領土争奪戦争ではなく、イデオロギーの戦争でもあった。ドイツ帝国、オーストリア=ハンガリー帝国、ロシア帝国、オスマン・トルコ帝国といった「権威主義国家」は没落し、英国・フランス・米国といった「民主主義国家」が勝利を収めた。
また過酷な総力戦を戦い抜くためには大衆、女性、植民地などの被征服民族の協力が不可欠であり、その地位は相対的に上昇した。結果として、大戦後の世界には「民主主義」を賛美する政治的、社会的風潮が広がっていくことになる。
変化は国際政治にも現れた。帝国主義的膨張政策は明確な非難対象となり、1920年に初の本格的集団安全保障機構たる国際連盟が設立された。1921年には日・米・英・仏・伊などの主要列強が参加してワシントン会議が開催され、太平洋地域と極東における現状維持と平和共存が約束された。いわゆる「ワシントン体制」である。
極東の島国日本もこうした潮流の例外ではなかった。1924(大正13)年に加藤高明内閣(護憲三派連立内閣)が成立すると、以後1932(昭和7)年に犬養毅内閣(政友会)が瓦解するまで、政党内閣が継続することになる。1925年には男子普通選挙法が制定された。大衆に支えられた政党が政権を担うことは「憲政の常道」となった。民本主義・社会主義・共産主義といった新思想が流行し、労働運動も盛んになった。
外交面では、憲政会・民政党内閣の外務大臣を歴任した幣原喜重郎がワシントン体制に則して「協調外交」を展開し、他方、政友会内閣でも国際紛争の武力解決を禁止する「不戦条約」(1928年)に調印した。
こうした当該期の政治・外交・社会・文化の新潮流や時代気分を一般に「大正デモクラシー」と呼ぶ。
「戦争屋」扱いされることになった日本軍
「大正デモクラシー」は陸軍を取り巻く社会環境も変化させた。日露戦争においては勝利の最大の功労者として威信を高めた軍隊であったが、本格的な戦闘に加わらなかった第一次世界大戦の後には、国際的な平和潮流の中で、むしろ国民的人気を低下させていく。
人々は戦争の原因を際限のない軍拡競争に見出し、軍事力によって安全を担保しようとする政策そのものに懐疑的な視線を向けるようになっていた。軍人の権威主義的態度も「デモクラシー」の時代風潮に反するものと観念された。そうなると悲惨なのは軍人である。軍人は「国家の干城(盾と城)」から「ウォー・モンガー(戦争屋)」に転落してしまった。
国民、特に都市部住民やインテリ層の軍人に対する視線は冷たいものとなった。新聞や雑誌は公然と軍部批判の論説を掲載するようになる。軍人はときに露骨な侮蔑や非難の対象となり、軍服姿で街を往来することを忌避するようになる。世論の変化は軍人志望者数に露骨に反映された。各種軍学校の志願者は激減し、合格しても入校を辞退するものが続出する。志願者の減少は必然的に質の低下にも結び付く。若い将校は結婚難にも苦しめられるようになった。