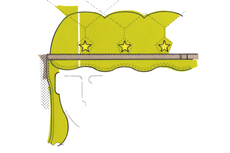陸軍がこうした対応に出た背景には、第一には、もちろん軍隊に対する国民世論を改善したいという切実な動機があった。
第二には、第一次世界大戦によって登場した国家総力戦という新しい戦争概念に対応するためでもあった。新時代の戦争が単なる軍事力だけではなく、経済・科学・教育・宣伝といった国家の総合力によって争われる以上、軍人といえども非軍事分野の知識の習得は不可欠だと考えられたのである。
第三には、兵士の質の変化に対応するためでもあった。陸軍の兵士は大半が徴兵によって充足されており、その質は社会の変化を鋭敏に反映する。都市化や国民の知的水準の上昇によって社会問題に関心のある兵士が増えた。必然的にこれを指導する将校にも、一定レベル以上の学識と理論武装が要求されるようになったのである。
日本陸軍曰く
「民主的軍隊は軟弱に見えても、その柔靭性で勝利を収める」
第四には、こうした兵士の質的変化を陸軍では必ずしも否定的なものとばかりは認識していなかった。それは陸軍が理想とする兵士の性格が変わりつつあったからである。
戦闘の苛烈化によって、兵士が密集していることによる全滅を避けるために戦闘形態の散兵化(散開戦術)が進むと、将校が末端の兵士を掌握することが難しくなる。結果として、個々の兵士に自主的判断が求められるようになり、兵士に要求される思考力レベルが上がることになる。また戦車や航空機など新兵器の登場や戦闘の複雑化によっても、末端の兵士に一定以上の知能が要求されるようになった。
何より「民主主義国」である英国・フランス・米国が勝利し、「権威主義国家」であるドイツ帝国やロシア帝国が敗北したことから、民主的軍隊は一見軟弱に見えても、その柔靭性において終局の勝利を収めるものと考えられたのである(もちろんこうした認識に反発する意見も常に存在したが)。
第五には、身も蓋もないが「大正デモクラシー」期が「平和」であったからである。国際連盟やワシントン体制が平和維持のスキームとしてどれほどの実際的効果を発揮していたかは慎重な考察が必要だが、少なくとも連盟やワシントン体制が平和維持スキームとして期待できた程度には世界が「平和」であったことは事実である。
そして平和な時代であったからこそ、陸軍は自己反省し、迂遠な理想主義的改革を試みる余裕があった。もし対外的緊張が高かったならば、こうした改革の優先順位は下がり、純軍事的な対応を先行させざるを得なかっただろう。
いずれにせよ「大正デモクラシー」に戸惑いつつも、陸軍は確かに変わりつつあった。そこにはわれわれが良く知る大日本帝国陸軍像とは異なる変革イメージが確かに存在した。しかし皮肉なことに、変革の可能性は「デモクラシー」の熟爛の中で失われていくのである。