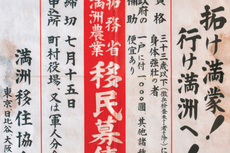――精神科を受診すると「通院精神療法」の名義の診療報酬を支払っているにもかかわらず、薬物療法のみというのは精神科医が精神療法を行えないからなのでしょうか?
井原氏:そう言わざるをえません。患者さんが精神科医に求めているのは、「薬の自動販売機」ではありません。しかし、精神科医の中で精神療法を得意としている人は少ない。とりわけ深刻なのは、大学病院です。教師陣に精神療法が得意な人が少ないんですね。
ただ、精神療法への患者さんの期待が非現実な場合もあります。精神療法には、できることとできないことがあります。精神療法は魔法ではなく、かけてもらえばパッと治るようなものではありません。患者さんの努力も必要です。患者さんに自分のこころや行動に気づいてもらい、自分の力で生活を変え、習慣を変え、行動を変えていただかねばなりません。治療とは第一に、患者さんに危機意識をもっていただくことなのです。
しかし、患者さんは驚くべきことに精神科医に癒しを求めてくる。患者さんのニーズと、本人が自覚すべき課題との間には、巨大なギャップがあります。それを埋めていく作業も精神療法の大切な要素です。そのためには患者さんと医師とで話し合いをしなければなりません。そういうトレーニングが大学病院では不足しているのですね。
――うつ病啓発キャンペーン当時、先生は順天堂大学病院で診療にあたられていて、患者さんが増えたなという実感はありましたか?
井原氏:昔は精神科を訪れる患者さんというのは、自らの意志で来るというよりは、ご家族に連れられて来るような人が多かった。しかし、ここ14、5年自ら進んで来る患者さんが明らかに増えましたね。ただ、それは悪いことではなく、我々医師としてはそういった新しいタイプの患者さんにもご奉仕させていただかなくてはいけないと思います。
しかし、自らの意志でやって来る方々は、「悩める健康人」であって、「脳の病気」ではない。ところが、精神科医は「悩める健康人」と「脳の病気としてのうつ」とを区別することができません。それに「悩める健康人」にどうご奉仕させていただいたらいいかわからない。それで、とりあえず来院された以上は「病気だろう」とみなして、薬を処方しました。
薬は病気を治すためのもの。健康を創るためのものではありません。それを「悩める健康人」に処方したのは大失敗でした。この人たちに必要なのは、「健康に悩む」ように導くこと。決して病気として治療することではありません。2000年代に精神科医たちが行ったことは、「悩める健康人」を十把一絡げに「病気」と見なし、抗うつ薬を無差別投与したことです。今は、反省期にはいったといえます。