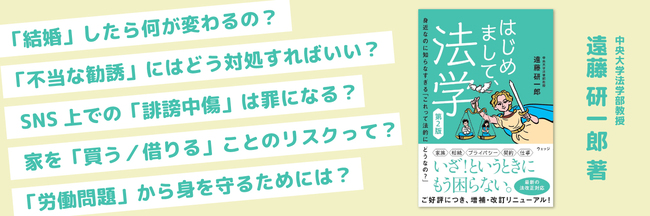まず、「あの映画は、おもしろくない!」といった類は、意見・論評です。そして、これは、合理的であるかどうかを問わず、人身攻撃のような逸脱したものでない限り、広く責任を問われるべきではありません。これが規制されてしまったら、私たちは、自分の意見などを自由に言えなくなってしまいます。
これに対して、「あいつには、過去に補導歴がある」といった類は、事実の摘示です。事実の摘示の公表によって社会的評価が下がれば、名誉毀損となる可能性があります。
ただし、事実の摘示であっても、不法行為にならない場合があります。とくに、その事実に「公共性」があり、また、「公益目的」からなされた摘示であれば、それが「真実」である限り、責任を問われません。
たとえば、公的な存在である政治家が、特定の会社に口利きをしたという記事は、それが真実である限り、国民の知る権利とつながり、表現の自由・報道の自由が保障され、名誉毀損にはならないと考えられます。
また、摘示した事実が「真実」だと証明できなかったとしても、摘示した事実が真実であると信じたことについて過失がないときには、責任は問われません。信頼できるところから情報を入手し、合理的な注意をもって調査・取材・検討した結果、報道したと認められれば、責任を免れることができます。
社会問題となった「誹謗中傷」
また、名誉を毀損したとはいえなくても、犯罪になる可能性もあります。たとえば、「侮辱罪」です(刑法231条)*3。侮辱罪は、名誉毀損罪のような事実の摘示がなくても、公然と他人を侮辱することによって成立する犯罪です。「バカ」、「クズ」、「ゴミ」、「デブ」、「ハゲ」など、他人を誹謗中傷するような表現が、幅広く侮辱罪の対象となります。
なお、近時、SNSの発達によって、私たちが積極的に情報発信できるようになったことと引き換えに、ネット上での誹謗中傷の書込みが社会問題となっていますね。そして、その書き込みが原因で、自ら命を絶つという事件なども後を絶ちません。
そのような中で、2022年に、侮辱罪が厳罰化されました。これまでは、侮辱罪の場合、拘留または科料という軽い刑罰しかありませんでしたが、改正によって、懲役刑もありうるようになりました。
さらに、「信用毀損罪」(刑法233条)*4にも触れておきましょう。名誉毀損罪が「名誉」に対する犯罪であるのに対し、信用毀損罪は「信用」に対する犯罪です。ここでいう信用とは、おもに経済的な面での社会的評価を指します。たとえば、ウソと知りながら、「このお店は、倒産寸前です」などという情報を流した場合、信用毀損罪が成立する可能性があります。
なお、ここで紹介した侮辱罪や信用毀損罪においても、刑事罰とともに、民事上の責任(損害賠償)に問われることは、言うまでもありません。
*3 【刑法231条】事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
*4 【刑法233条】虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。