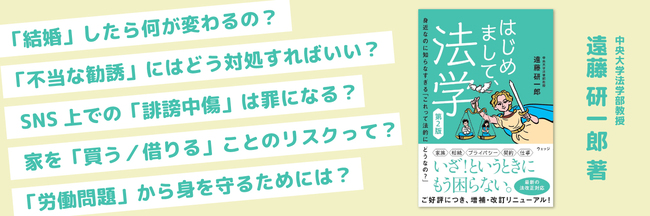連続テレビ小説『虎に翼』(NHK)、日曜劇場『アンチヒーロー』(TBSテレビ)など、法曹の世界に生きる人々を描いたドラマが話題を呼んでいます。法は、自然科学のような不変の法則とは異なり、「解釈」を変えることによって、あるいは「立法」することによって、時代に応じて変化を続けています。
今回の記事では、法的な視点から「財産権」について解説。財産権は、憲法にも明記されている基本的人権のひとつですが、法的な制約が正当化されるのはどのようなケースなのでしょうか。
*本記事は中央大学法学部教授の遠藤研一郎氏の著書『はじめまして、法学 第2版 身近なのに知らなすぎる「これって法的にどうなの?」』(ウェッジ)の一部を抜粋したものです。
今回の記事では、法的な視点から「財産権」について解説。財産権は、憲法にも明記されている基本的人権のひとつですが、法的な制約が正当化されるのはどのようなケースなのでしょうか。
*本記事は中央大学法学部教授の遠藤研一郎氏の著書『はじめまして、法学 第2版 身近なのに知らなすぎる「これって法的にどうなの?」』(ウェッジ)の一部を抜粋したものです。
憲法で守られている「財産権」
憲法29条を見てみると、基本的人権の1つとして、財産権が明記されています。
憲法29条1項
財産権は、これを侵してはならない。
財産権は、これを侵してはならない。
個人が有している具体的な財産上の権利(財産権には、所有権以外にも、さまざまな権利が含まれます)を、憲法上の基本的人権の1つとして保障しているのです。たとえば、自分が所有している時計を、何の合理的根拠もなく誰かに奪われることはありません。
同時に、憲法29条1項は、個人の財産上の権利を直接的に保障するだけではなく、個人が財産を取得し保持する権利の前提となる制度一般(すなわち「私有財産制」という制度)を保障しているという側面があります。
財産に対する私的な権利を認めるという法的な制度が認められないと、そもそも、所有権を含む財産権という概念自体が成り立たなくなってしまいます。ですから、財産権の前提となる私有財産制という制度も、この条項で保障していると考えられます。