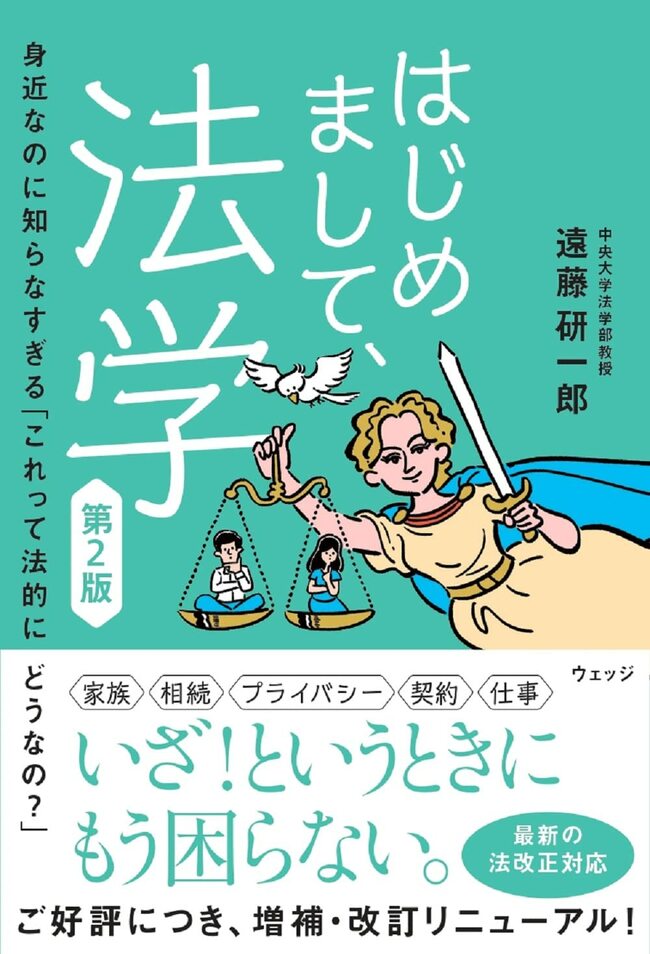「これは私の物!」には限界がある
財産権は、資本主義の根幹をなすものであり、私たちにとって必要不可欠な権利です。ですから、基本的人権のカタログの1つとして、憲法が保障しているのです。
しかし、何の制約も存在しないというわけではありません。とくに、「公共」という面から制約が正当化される場合があります。
財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
憲法29条2項は、財産権の内容が、公共の福祉の観点から、法律によって制約され得るものであるということが示されています。では、具体的に、どのような制約が認められるのでしょうか。
まず、他人の生命や財産を守るという観点からの規制があります。たとえば、消防法5条1項*1には、建造物などについて火災の予防上必要があると認められる場合、消防長または消防署長から、その物の改修・移転・除去など必要な措置を命じられることがあると規定されています。自分の所有する建物であっても、周囲の安全が脅かされないよう、一定の制約があるのです。
また、社会政策・経済政策上の観点からの規制も可能です。たとえば、借地借家法の例を挙げましょう。アパートの賃借人は、たとえ賃貸借期間が満了したとしても、賃貸人(いわゆる、大家さん)に、契約の継続(更新)を求めることができます。そして、借地借家法28条*2によると、大家さんは、「正当の事由があると認められる場合」でなければ、更新を拒絶することができないものとなっています。
自分が所有する建物であっても、そして、アパートの賃貸借契約の契約期間はきちんと満了していたとしても、正当事由がないと、大家さんは賃借人に立ち退きを求めることができないのです。ここには、アパートの借主を保護する(借主の居住環境を確保する)という政策があります。
私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
さらに、憲法29条3項は、私有財産を公共のために用いることができるとしています。私有地であっても、学校、鉄道、道路、公園などといった公共のために用いるのであれば、国が強制的に収用したりすることもできるのです。
なお、その際には正当な補償が必要ですが、どのようなことをすれば「正当な補償」をしたということになるのかについては、争いがあります。
私は、国民一般の利益のために特定の人の財産権に制約が加えられている以上、その損失補償は、市場価格による完全な補償(ただし、生活補償は除く)がなされることを基本とすべきであると考えますが、その点は見解が分かれるところです。
*1 【消防法5条】①消防長又は消防署長は、防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況について、火災の予防に危険であると認める場合、消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合、火災が発生したならば人命に危険であると認める場合その他火災の予防上必要があると認める場合には、権原を有する関係者(特に緊急の必要があると認める場合においては、関係者及び工事の請負人又は現場管理者)に対し、当該防火対象物の改修、移転、除去、工事の停止又は中止その他の必要な措置をなすべきことを命ずることができる。(後略)
*2 【借地借家法28条】建物の賃貸人による第26条第1項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。