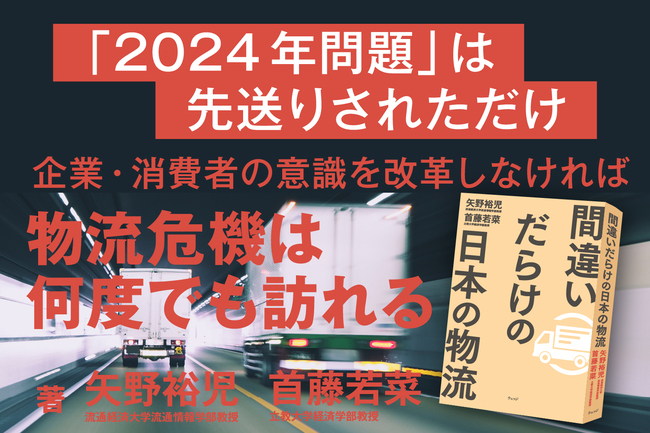水産品を運ぶ現場の実態
2024年4月以降も水産品の輸送を手がける運送会社の事例を紹介しよう。水産品は、活魚、鮮魚、魚種、地域、加工品などによって荷物形態が異なり、抱える課題も違うが、ここでは魚介類を生きたまま運ぶ活魚輸送の現場を見る。
活魚を専門とする運送会社によれば、荷物の積み込みは未だにトラックが到着した順番に行われることが多い。産地から東京に活魚を運ぶには、できるだけ早い時刻に積み込む必要がある。そこで朝6時から始まる積み込みに備えて、車の台数が多い時には、順番取りのために前日の20時や21時に現場に入る。積み込み時間は、1台あたり約2時間かかるため、順番が遅くなれば、待機時間が長くかかる。同社は「運送会社としては、どうすることもできない。荷主と生産者の問題であって、運送会社はそれに従うしかない」と話す。
積み込みが終われば直ちに出発し、首都圏まで活魚を運ぶ。同社では、改善基準告示が定める4時間の連続運転後に取得する30分休憩や、市場に到着して荷物を卸した後に休息期間を9時間以上取得することは徹底してきた。しかし、告示が定める1日の拘束時間(原則13時間以内、上限15時間)を守ることができない。鮮度が要求される往路は、産地から市場まで15~17時間を要するためだ。
他方で、復路は休息期間を確保するために、フェリーに乗ることにした。「せめて復路だけでも、告示を遵守したい」と同社社長は話す。だが、往復で2日要した運行が3日になることで、輸送効率が低下している。加えて、首都圏よりも遠い場所への出荷は減らさざるを得なくなった。
しかも、復路をフェリーに変更したことは、ドライバーたちから不評だ。船で帰れば自宅で休む時間が少なくなり、家族と過ごす時間が減ってしまうためだ。それを理由に、同社を辞めていったドライバーもいる。
また、フェリーに乗れば、フェリー代金がかかるため、運賃の値上げが必要となる。しかし、それに見合った運賃上昇は実現していない。少しでも運賃を上げれば、仕事が減ってしまうという。同社は厳しい状況に立たされている。