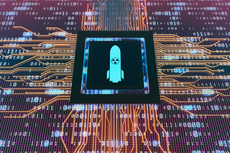アメリカのトランプ大統領によるハーバード大学の留学生受け入れ制限問題を受けて、香港政府のトップである李家超(ジョン・リー)行政長官は香港以外の学生の受け入れ枠の上限を20%から40%に引き上げたほか、香港の各大学も留学生も受け入れを表明した。これは、2019年の逃亡犯条例改正案に端を発した大規模デモや20年に制定された香港国家安全条例によって傷ついたイメージ回復を図りたい狙いがあるほか、中国政府としても香港が受け皿となることで、アメリカに流出していた優秀な中国人を引き戻せるという思惑があるものとみられている。
留学が身近な香港
ハーバード大の留学生の問題が出た時、日本社会の全体の雰囲気は「かわいそう」が多く、受け入れまで考える人はそうは多くなかった。しかし、香港人は現在の政治の話は別として、国際金融都市で、物流のハブであり、フリーポートで、英語が公用語であることもあり、人材獲得のチャンスと捉えた。
香港は小学校から大学まで、TSA、SSPA、HKDSEなど日本でいうセンター試験のようなテストがあらゆる節目にある。どんどん振るいに掛けられるため、香港内の大学に進学することすら大変だ。そのため、イギリスなど海外に留学する香港人も多数いる。留学は香港人にとって特別なことではないという下地がハーバード大の留学生を「かわいそう」ではなく「香港に彼らを呼べる」と考える人が多い。
こういう背景があるからこそ、香港の各大学はハーバード大の留学生の受け入れをすぐに表明できた。そこに、政治的意図が絡めばよりスピード感がより加速するのは必然だった。