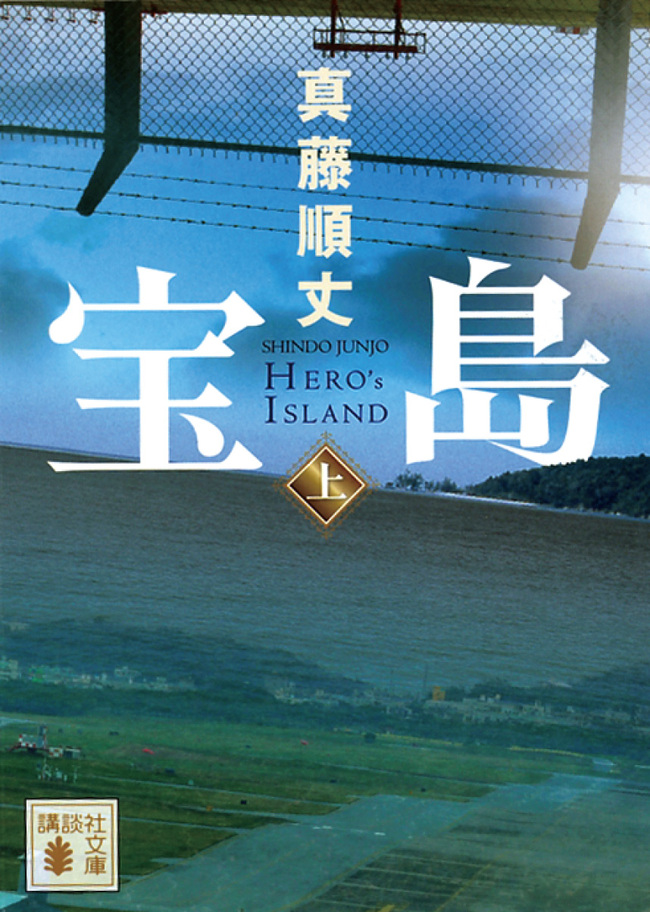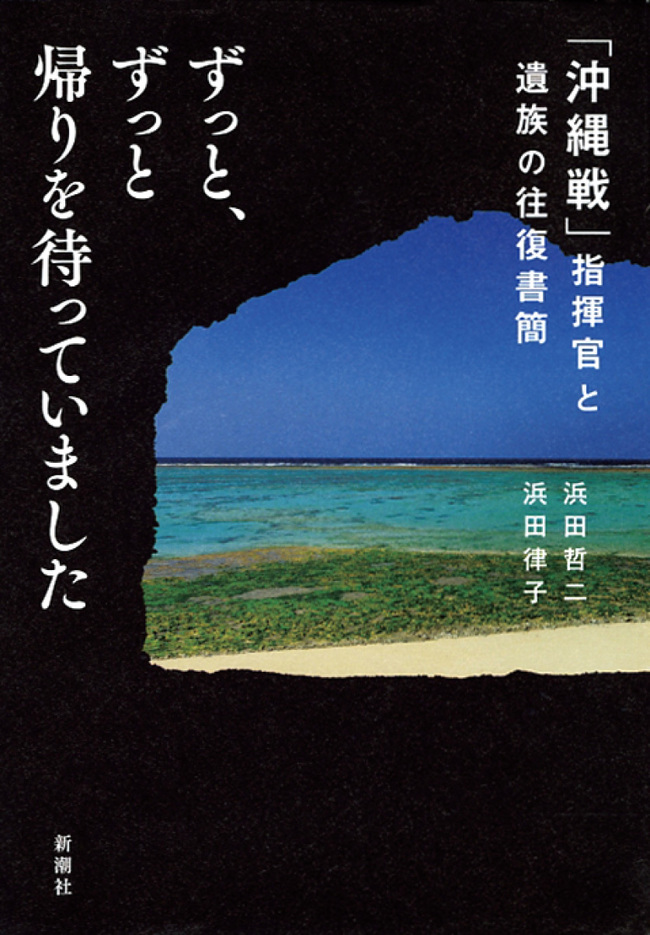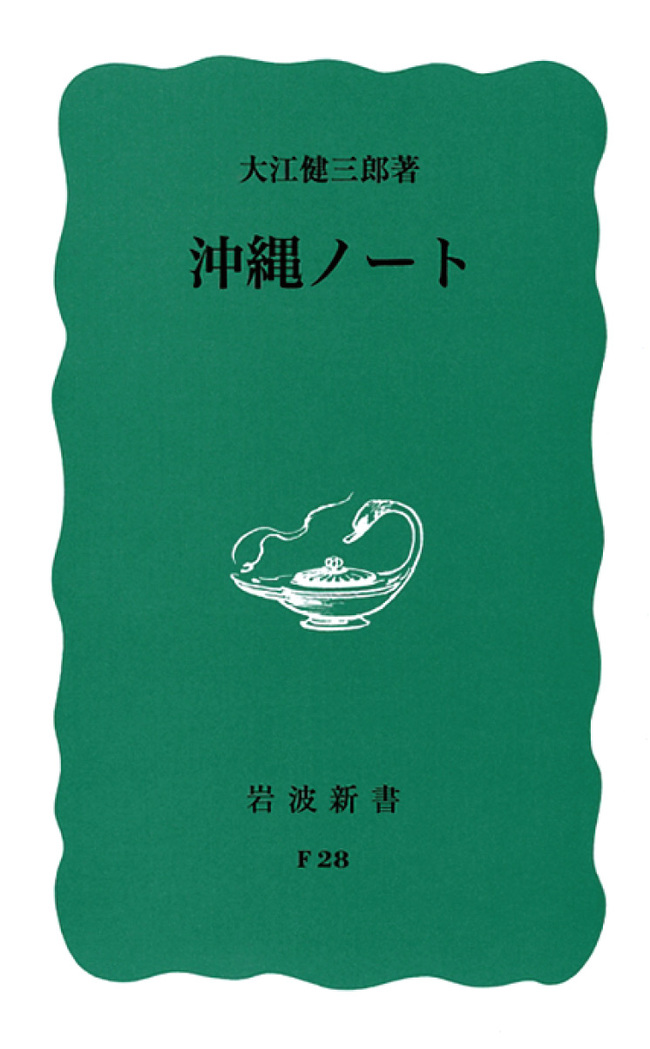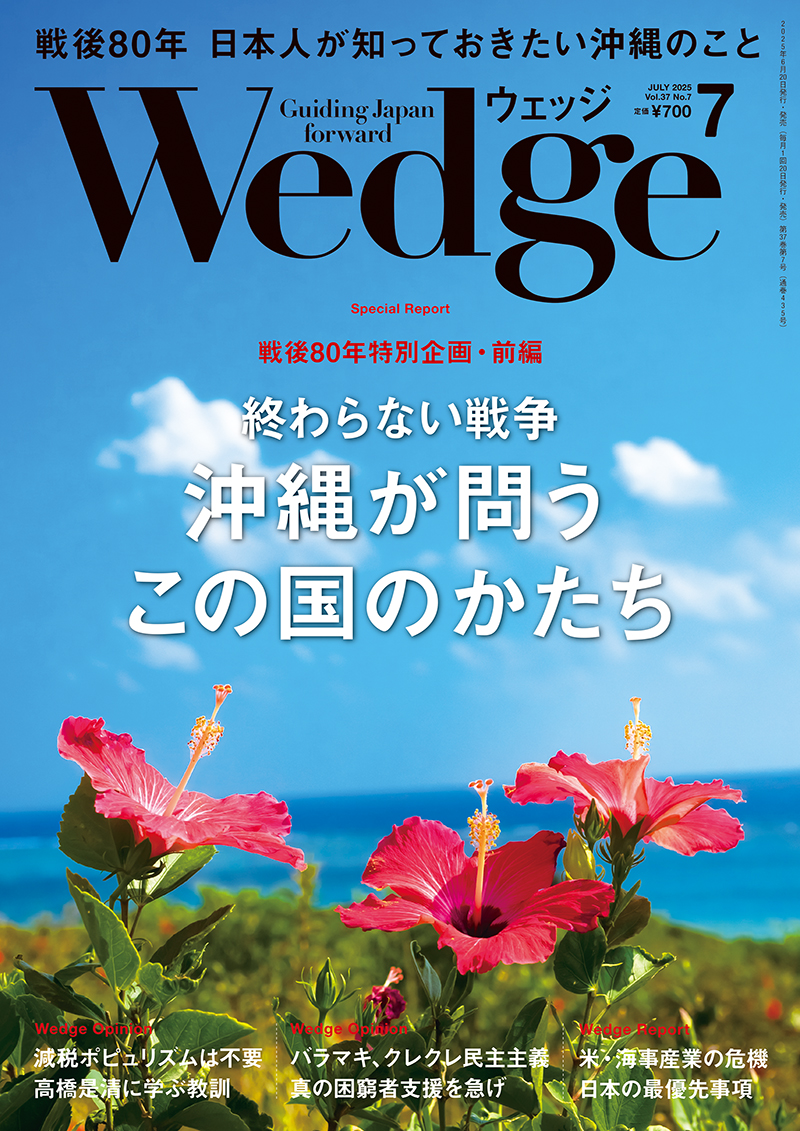故郷に命を懸ける
宝島 真藤順丈 講談社文庫 924円(税込)
米国統治時代の沖縄。「戦果アギヤー(戦果をあげる者)」と呼ばれる若者たちがいた。基地に入り、食料品などを盗み出し、苦しい生活をする人々にも配った。そんな実在した若者たちが本書の主人公。かつてない「戦果」を狙って侵入した嘉手納空軍基地。ここで、皆の英雄だった兄貴のオンちゃんが消えてしまう。なぜか? 宝とは何か?……。登場人物たちは少年少女時代に沖縄戦で親を亡くしており、米軍基地があるがゆえに起きる理不尽が襲いかかる。物語の舞台は「コザ暴動」までだが、今に続く沖縄の人々の苦悩が描かれた第160回直木賞受賞作品である(文庫版上下巻)。
沖縄戦の戦死者遺族の手紙
「沖縄戦」指揮官と 遺族の往復書簡 ずっと、ずっと 帰りを待っていました 浜田哲二、浜田律子 新潮社 1760円(税込)
24歳にして約千人の部下を率い、沖縄の激戦地を生きた伊東孝一大隊長は、復員後、戦死した自身の部下の遺族に向けて600もの詫び状を送っていた。本書の書き手は、詫び状への返事である356通もの遺族からの手紙を、存命する遺族に返還して、故人やその後の家族の話を聞いていく。自身の夫や息子の戦死を知り、それでも前を向き「新日本建設」への誓いを文章にしたためる家族、一方で国による戦死者の扱いを嘆く家族……。終わらない戦争がまざまざと書かれている。
沖縄の見方の一つとして
沖縄ノート 大江健三郎 岩波新書 1034円(税込)
1965年春に、初めて沖縄を訪れたことを皮切りに、その地に何度も足を運んだ大江健三郎。そこでの取材や見聞きした内容を通して、何を感じ、何を考えたのかが文学的に表現されている。沖縄を見つめる中で改めて日本人とは何かを考え直す同氏が、実は「多様性にたいする漠然たる嫌悪の感情」を持つ国民なのではないか、など葛藤する様子も印象的だ。出版は本土復帰前の70年。メディア報道とは違う目線で語られた本書から、当時の沖縄の一面を垣間見ることができる。