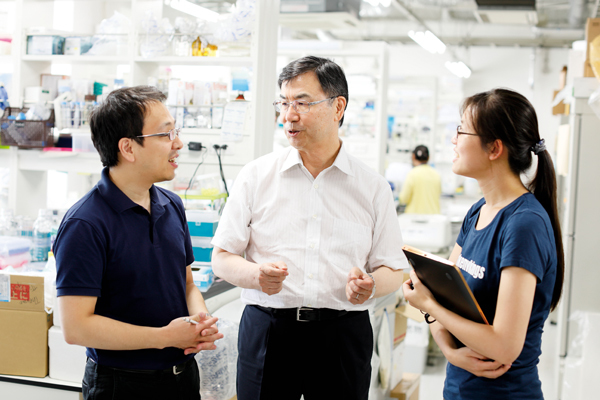京大の大学院に進み、研究者の道を本格的に歩み出した坂口は、ある日、医学誌で愛知県がんセンターの西塚泰章(やすあき)教授たちの論文「免疫細胞をつくる胸腺を摘出したマウスの実験」を目にした。胸腺で作られるT細胞には、異物を排斥する司令塔のヘルパーT細胞と攻撃するキラーT細胞があり、理屈ではそれらを取り除いてしまえば免疫反応は起きなくなってしまうはずだ。しかし、なぜか結果は逆で、免役反応が過度に表れてさまざまな臓器への攻撃を始めるというものだった。もしかしたら取り除かれたT細胞の中には、攻撃だけではなくブレーキをかける未知の細胞も含まれているのではないか。覗(のぞ)き込んだ深淵に何かがチラッと見えた。
坂口はすぐさま大学院を中退し、愛知県がんセンターの研究生になった。心が動くものがあったらまっしぐら。求めるものに頑固で動きは軽やかな研究者としての姿勢がうかがわれるエピソードである。
しかし坂口にとって不運だったのは、当時は、免疫反応を抑える「抑制性T細胞」なるものが存在するという仮説が提唱され世の注目を浴びたものの、ヒトの疾患との関連が見えないままサイエンスとしての証明ができずに、やっぱり存在しないと否定された時期だったこと。時流に逆行し、まさに研究者が次々下船している船に乗って、真冬の海に乗り出すような出発だったのだ。
「でも、僕の目の前で起きている現象は明瞭なんです。自分は自分の方法で自分の仮説を追おうと決めました」
そしてついに、否定された抑制性T細胞とは違う、免疫を抑えることに特化した制御性T細胞が常に体内に存在することを突き止め、学位論文としてまとめ上げた。が、一度傍流へと外れた仮説を育ててくれる土壌は日本には存在しない。アメリカに渡り、さまざまなフェローシップに応募して研究が続けられる道を模索するしかなかった。
「日本で傍流はアメリカでも傍流なわけでね。でもアメリカの懐が深いのは、世の中の流れとは違うけど面白いんちゃうかと思えばどんとお金を出してくれるところがあること。8年間研究費と生活費をサポートしてくれる奨学金制度があって、研究を続けることができました」
もしアメリカで奨学金が得られなかったら? 恐る恐る発した質問に、「スゴスゴと帰って何か仕事を見つけなきゃならなかったでしょうね」と坂口は笑った。